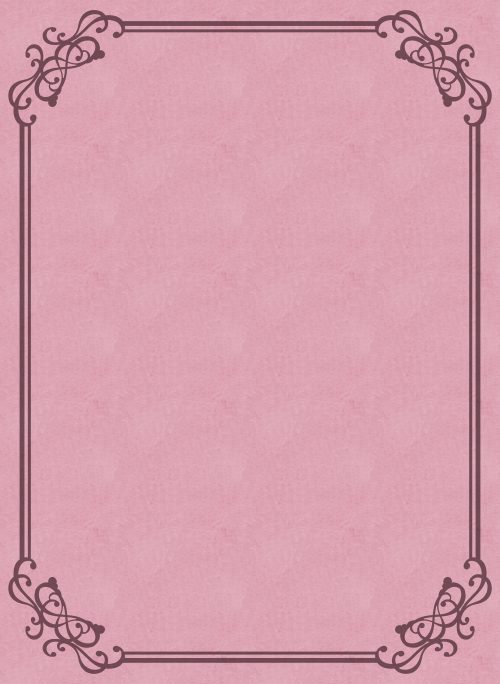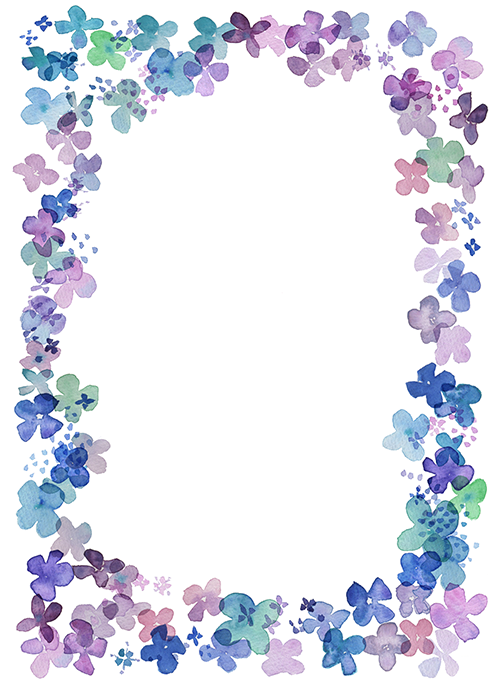自分から傍へ来たくせに、所在無げに突っ立って、あたしの視線は宙を泳ぐ。
焦りを感じ、上ずった声が発したのは
「偶然だね? こんなとこで会うなんて」
他愛もない、そんな言葉だった。
自分で自分に戸惑ってしまう程、その時のあたしは酷く余裕がなくて。
だから、ハルが静かに口にした台詞を聞いた時、当然ながら一層落ち着きを無くしてしまった。
「今のって、婚約者さんですか?」
ハルの目線は、さっきまでタダシが歩いていた方向を向いている。
返事もできないまま、ハルが何故あたしに婚約者がいることを知っているのだろうかと考えた。
じわりと気まずい気持ちが胸に広がる。
と同時に、今の自分は変だと思った。
そんな心の内が顔に出ていたのかもしれない。何も答えられないことを察したかのように、伏目がちにハルが続けた。
「サクラさんの誕生日にマンションへ行った時、オレ、見ちゃったんです。
ごめんなさい。読むつもりはなかったんですけど。床の上に置きっぱなしだったプレゼントに気づいて、拾い上げた時にカードが落ちて……」