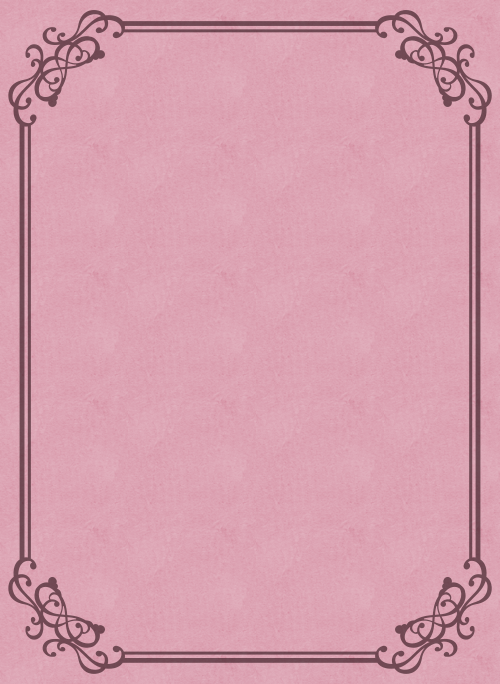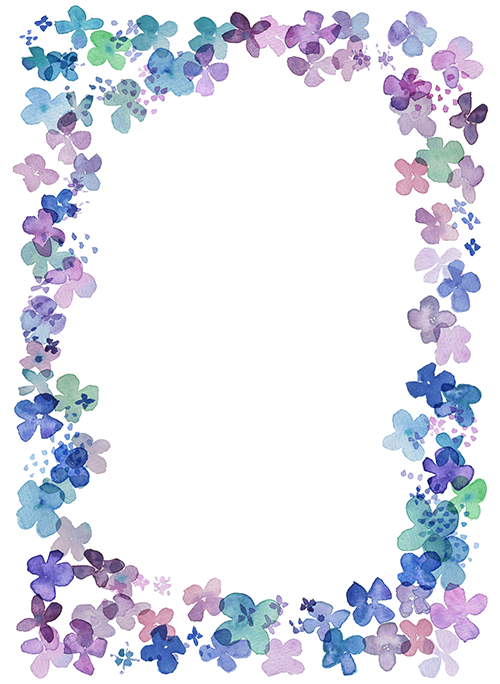長い海外出張から帰ってきたばかりなのに、こんな話をするのは流石にどうかと思った。
俯き気味に眉間に皺を寄せるタダシを前に、後悔の気持ちだって募った。
でも彼は、そんな心配を余所に歪めていた顔をすぐに戻したんだ。
強張っていた表情を一瞬で正し、静かに言った。
「それでいいんじゃないの?」
口元に小さな笑みさえ浮かべている彼に、戸惑ってしまう。
「これから何十年も連れ添うのに、最初から熱を持ち過ぎてるのもどうかってことだよ。
“愛”だの“好き”だの飽きるまで囁いて、それを相手にまで強要する。そんなパートナーと一緒にいても疲れるだけじゃないか?
それに、そんな感情は大体一時のものなんだから、持ってるだけ無駄だってこと。そう思わないか?」
そして、持っていた煙草を静かに灰皿へ押しつけて“御品書き”に手を伸ばし
「でも、ちょっと意外だったね。サクラがそんなことにこだわるなんて……案外、普通なんだな」
と鼻で笑った。
「毎日会いたい、決まった時間に連絡して欲しい、 そんなバカげたことを言わないから君を選んだのに。
月並みな詰まらなさを持ち合わせていたなんて、ね」
「………」