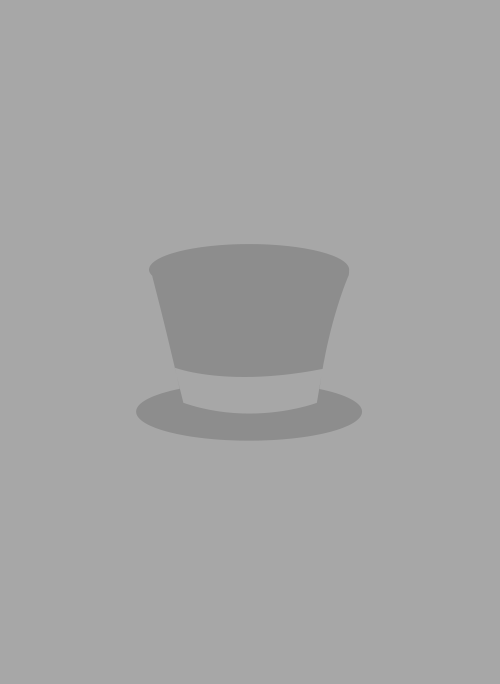いや、この状況であれば助けられないのも納得だ。
それは、遥か上の力を持つ女王が太刀打ち出来ない相手に、自分達が挑んでも意味がないと言う事。
それに顔は地獄の鬼のような形相の礼子でも、不思議と女王が殺されるような危機感は感じなかったからである。
無論、自分の娘に殺意を向ける親はいない。
そんな躾の一環を漂わせる雰囲気が、使者霊の安心感に繋がったからだ。
「ふう……このくらいにしとくかな」
お尻がリンゴの様に真っ赤に腫れ上がった里子は、お仕置きからようやく解放された。
てか、叩き過ぎ。
「いたた……あ、アナタは一体何者ですか? 階級10の私をいとも簡単に抑えつけるなんて……」
涙目ながらも、礼子の正体を聞いてきた。
一応隠しておこうか?
そう思い、女王に対して背中を向けた。
「ふ。大きくなったわね里子。これからもこの世界を頼んだわよ。下になめられないように立派にやりなさい」
いやいやいや。
思いっきりシバいといて、そのセリフはないわ。
そのまま去ろうとすると、女王は引き止めた。
「ま、まさか……お母さん!?」
それを言っても、礼子は振り返らず軽く手を上げた。
ルー♪ルルルル~~~♪
その哀愁漂わせる背中を見せ付け、夕日(ないけど)に向かって歩いて行った。
完全に、何か役に入っている礼子であった……