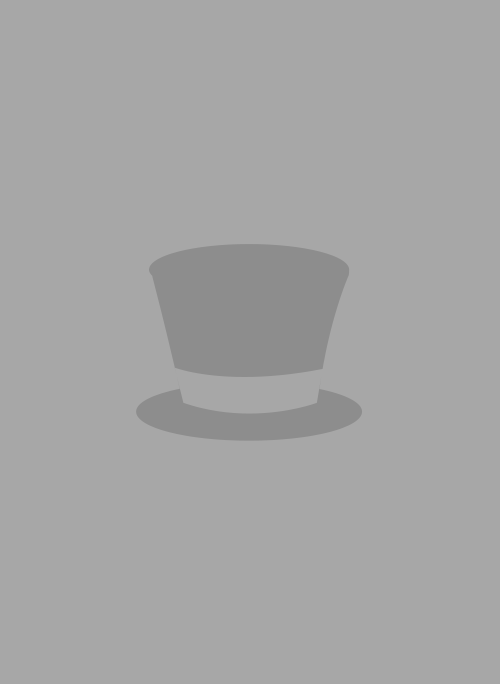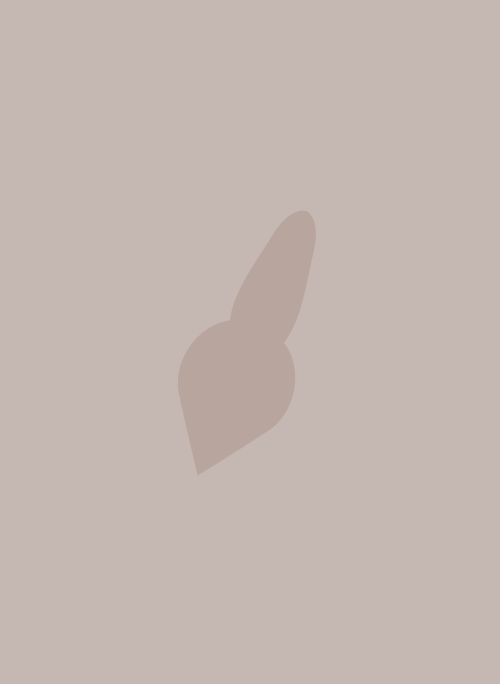「フッうまくいった。この傷の礼は、またいつかな眠り猫よ。サラバだ」
再び黒ガラスは走り去り、姿を消してしまった……
それを、ただ見てるしか出来ない2人。
体が虎砲で動かないのだ。
「クソぅ!! 逃げられたか!」
数秒後、ようやく痺れが取れ始めた時は、完全に黒ガラスの気配も失っている。
やられたか。
オッサンはガックシ膝を付くと、眠り猫はまだ諦めていない様子を見せた。
「体が軽い……ようやく我が輩のスピードが完全に戻ったか……オイ、メガネ。アイツを追いかけるぞ。この血の後を辿ろう」
残された手掛かりである、黒ガラスの霊血。
この方向に、行ってみようとの事だ。
「それでも、もう間に合わないんじゃ……」
その諦めモードを振り払うように、眠り猫はオッサンの手を掴んだ。
「まあ見てニャって、全開絶頂の我が輩の速さを……」
シュン!!
その言葉の瞬間。突然、目の前の風景が消えた。
いや、そう見えたと言った方が正しい。
眠り猫は走ったままオッサンを引っ張り、目にも止まらぬ物凄いスピードを体験させた