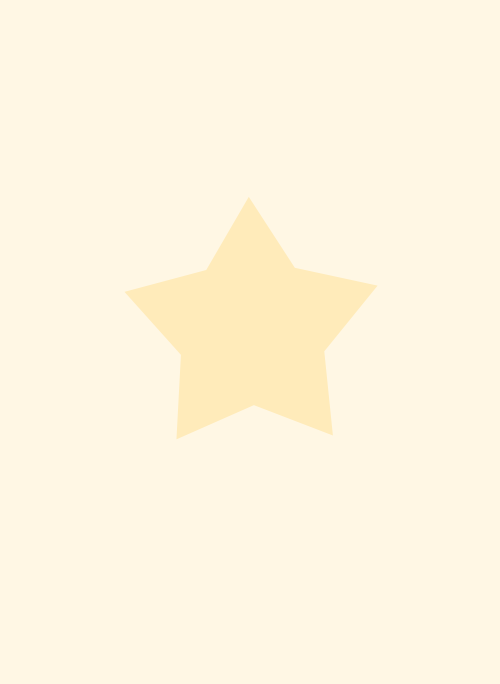「兄ちゃんが何でも聞いてやる」
誠治は改めて、桃子の方を向いた。
「告白したの。卓也さんに」
「たくや? 卓ボンか」
「卓ボンって言わないでよ」
「卓ボンは卓ボンじゃないか」
「安っぽく聞こえるから」
「桃子、タクという名がついた以上、世間様でタクボンと呼ばれるのが、いにしえからの習いだ。邦画が好きな奴じゃないと、この話の真意はわからない」
「それ、やだよ」
「お前はまだ、世の中のことを分かってはいないだけだ」
「知りたくもないよ」
「世間の荒波は、すぐそこまでやって来ているのだ」
「お兄ちゃん、話を戻していい?」
「あっ、そうだな」
「だから、卓也に告白したのよ。好きだって」
「そうか。直球だな」
「お兄ちゃんは桃子を応援してくれる?」
「毎日顔を会わせている可愛いい妹と、俺の素直で心優しい親友の卓ボンだ」
「お兄ちゃん……」
「お兄ちゃんは、いつだって桃子の味方さ」
兄の口からはいつもツルツル言葉が出てきて、桃子は内心は感心している。普段から口内炎を抱えているとは思えない流暢さだ。
しかし、今日の兄の言葉は、桃子にとって、堪らなく温かかった。
誠治は改めて、桃子の方を向いた。
「告白したの。卓也さんに」
「たくや? 卓ボンか」
「卓ボンって言わないでよ」
「卓ボンは卓ボンじゃないか」
「安っぽく聞こえるから」
「桃子、タクという名がついた以上、世間様でタクボンと呼ばれるのが、いにしえからの習いだ。邦画が好きな奴じゃないと、この話の真意はわからない」
「それ、やだよ」
「お前はまだ、世の中のことを分かってはいないだけだ」
「知りたくもないよ」
「世間の荒波は、すぐそこまでやって来ているのだ」
「お兄ちゃん、話を戻していい?」
「あっ、そうだな」
「だから、卓也に告白したのよ。好きだって」
「そうか。直球だな」
「お兄ちゃんは桃子を応援してくれる?」
「毎日顔を会わせている可愛いい妹と、俺の素直で心優しい親友の卓ボンだ」
「お兄ちゃん……」
「お兄ちゃんは、いつだって桃子の味方さ」
兄の口からはいつもツルツル言葉が出てきて、桃子は内心は感心している。普段から口内炎を抱えているとは思えない流暢さだ。
しかし、今日の兄の言葉は、桃子にとって、堪らなく温かかった。