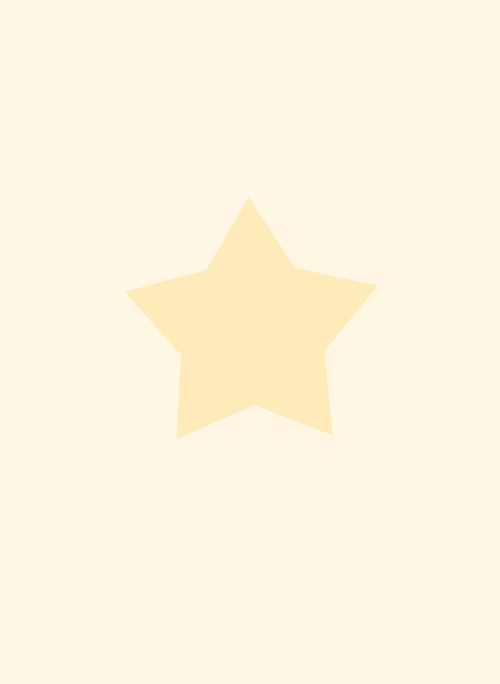「可愛い妹が作った手料理だ。食べるよ」
誠治は勢い良く食べ始めた。
「粗びき山椒が、よく効いていて、美味し過ぎて、涙が出てきたよ」
誠治は、本当にボロボロと涙を流しながら、桃子の手料理を完食した。
三人の食卓は、賑やかなうちに終わった。
その夜、桃子は、ひとり洗面所の鏡の前にいる誠治を見付けた。
「お兄ちゃん、今日はありがとう」
「麻婆豆腐、美味かったよ」
「山椒を効かせて、ごめんね」
「ごめんって、お前」
「涙流して食べているお兄ちゃんを見て、やっと気付いたの」
「何が解ったと言うんだ」
「私って、鈍感ね」
桃子はそう言うと、誠治の唇に指を添えた。
「バレてたか」
「解ったわよ」
「そうか」
「痛いんでしょ」
「泣けるほど、染みたよ」
「お兄ちゃんには、苦労かけたから」
「受験勉強のストレスだよ」
「ねえ、見せてよ」
「見るか」
「お兄ちゃんの痛みは、私の痛みでもあるから」
「では、妹よ。しかと見届けよ」
「しかと、見届けるから」
誠治は唇をめくった。
鏡に映ったのは、紛れもなく痛々しい口内炎だった。
「トライアングル・スペシャル、って言うんだよ」
誠治はニコリと笑った。
―完―
誠治は勢い良く食べ始めた。
「粗びき山椒が、よく効いていて、美味し過ぎて、涙が出てきたよ」
誠治は、本当にボロボロと涙を流しながら、桃子の手料理を完食した。
三人の食卓は、賑やかなうちに終わった。
その夜、桃子は、ひとり洗面所の鏡の前にいる誠治を見付けた。
「お兄ちゃん、今日はありがとう」
「麻婆豆腐、美味かったよ」
「山椒を効かせて、ごめんね」
「ごめんって、お前」
「涙流して食べているお兄ちゃんを見て、やっと気付いたの」
「何が解ったと言うんだ」
「私って、鈍感ね」
桃子はそう言うと、誠治の唇に指を添えた。
「バレてたか」
「解ったわよ」
「そうか」
「痛いんでしょ」
「泣けるほど、染みたよ」
「お兄ちゃんには、苦労かけたから」
「受験勉強のストレスだよ」
「ねえ、見せてよ」
「見るか」
「お兄ちゃんの痛みは、私の痛みでもあるから」
「では、妹よ。しかと見届けよ」
「しかと、見届けるから」
誠治は唇をめくった。
鏡に映ったのは、紛れもなく痛々しい口内炎だった。
「トライアングル・スペシャル、って言うんだよ」
誠治はニコリと笑った。
―完―