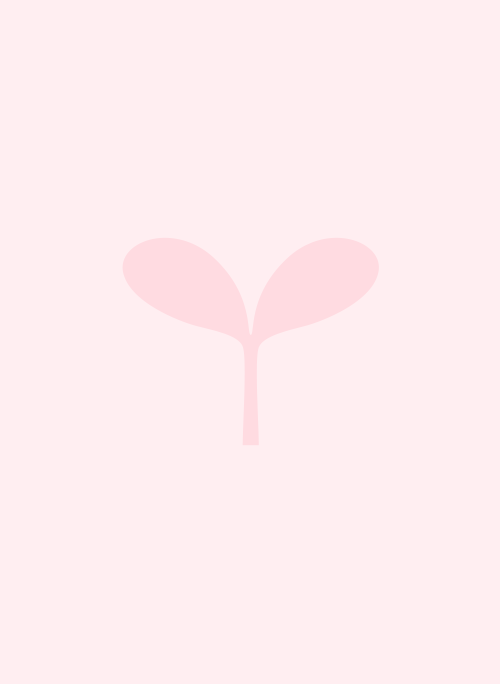「桃子、遅れるぞ」
「わかってるわよ」
高校一年生の桃子に、同じく高校三年生の兄、誠治との、朝の会話である。
同じ高校へ進んだ兄妹は、毎朝競い合って、一緒に家を出る。
兄の誠治を一言でいうと、包容力、という言葉が桃子には浮かぶ。体格的に大きいという単純な理由もあるが、何よりも桃子のことをいつも気に掛けてくれるのだ。
兄は頭は良く、桃子に優しい。学校の成績が良いのはいうまでもないが、下らない事を瞬時に話せる頭脳を持ち合わせていた。
「お兄ちゃん、靴ひも、ほどけているよ」
誠治の右足の靴ひもが、大胆にほどけていた。
「何、いかん。桃子、兄ちゃんを捨ておき、先に行ってくれ」
「下らないこと言ってないで、早く結びなさいって」
「わかったよ」
「お兄ちゃん。結んだ靴ひもの残りを、他のひもに押し込んでおくんだよ」
「ひもの余りを踏まないようにするんだな」
「蝶々結びの羽の部分も、押し込んでおくと、なかなかほどけないよ」
「そうか。豆知識だな」
「感心してないで、早く結んでよ」
「ほら出来た。桃子の話を聴きながら、手はちゃんと動いている」
誠治は桃子に言われた通り、きちんと結んでいた。
「お兄ちゃん、右脳と左脳を別々に動かせるとか言わないでね」
「大脳と小脳だ」
「脊髄で話をしてよ」
誠治と桃子は、取り留めのないやりとりをしながら、学校へ向けて走り出した。
父が仕事で海外へ出向になった折り、学校に通う誠治と桃子のために、母は日本に残ってくれた。
特に誠治は大学受験の年であり、家族の最大のイベントとして、最優先に考えるべきものになっていた。
そんな矢先、桃子に口内炎が出来たのだ。
「わかってるわよ」
高校一年生の桃子に、同じく高校三年生の兄、誠治との、朝の会話である。
同じ高校へ進んだ兄妹は、毎朝競い合って、一緒に家を出る。
兄の誠治を一言でいうと、包容力、という言葉が桃子には浮かぶ。体格的に大きいという単純な理由もあるが、何よりも桃子のことをいつも気に掛けてくれるのだ。
兄は頭は良く、桃子に優しい。学校の成績が良いのはいうまでもないが、下らない事を瞬時に話せる頭脳を持ち合わせていた。
「お兄ちゃん、靴ひも、ほどけているよ」
誠治の右足の靴ひもが、大胆にほどけていた。
「何、いかん。桃子、兄ちゃんを捨ておき、先に行ってくれ」
「下らないこと言ってないで、早く結びなさいって」
「わかったよ」
「お兄ちゃん。結んだ靴ひもの残りを、他のひもに押し込んでおくんだよ」
「ひもの余りを踏まないようにするんだな」
「蝶々結びの羽の部分も、押し込んでおくと、なかなかほどけないよ」
「そうか。豆知識だな」
「感心してないで、早く結んでよ」
「ほら出来た。桃子の話を聴きながら、手はちゃんと動いている」
誠治は桃子に言われた通り、きちんと結んでいた。
「お兄ちゃん、右脳と左脳を別々に動かせるとか言わないでね」
「大脳と小脳だ」
「脊髄で話をしてよ」
誠治と桃子は、取り留めのないやりとりをしながら、学校へ向けて走り出した。
父が仕事で海外へ出向になった折り、学校に通う誠治と桃子のために、母は日本に残ってくれた。
特に誠治は大学受験の年であり、家族の最大のイベントとして、最優先に考えるべきものになっていた。
そんな矢先、桃子に口内炎が出来たのだ。