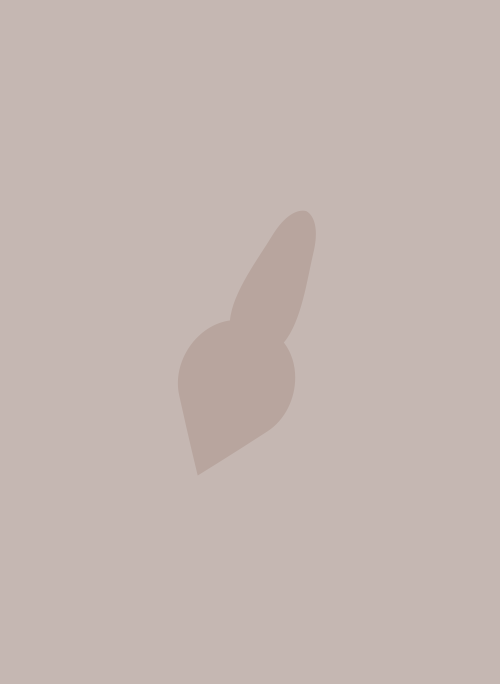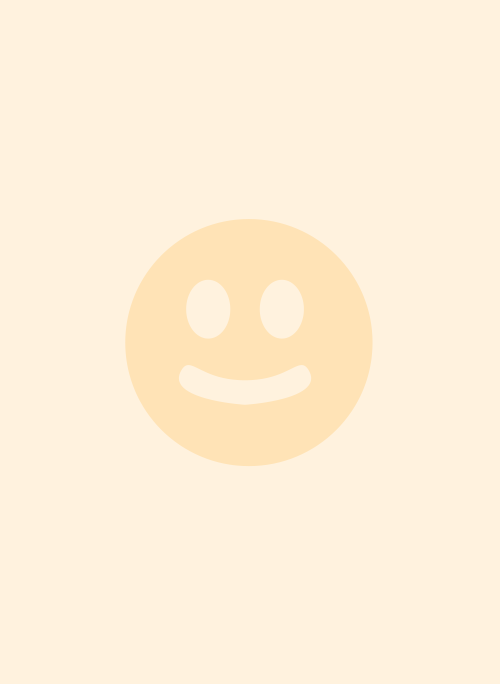あたしが次に目を開けたのは、多分朝。
太陽の光が降り注いで、とてもとても綺麗なはずなのに、この街はどこかつまらなく見えた。お化粧が剥がれたみたいに。
誰かがあたしを揺すぶっていた。
あたしは正直もう二度と目を開けたくなかったので腹を立てて、ひくうい声で、何、と問う。
その誰かは、ぱっとあたしから手を離し、
―ああ、良かった生きてた!
脳天気ににこにこと笑う。
その陽気さがやけに癇に障って、あたしはますます不機嫌になった。
―余計なこと、しないで。
あたしはいっそ八つ当たり気味に、腹を立ててあたしを罵って自分勝手に立ち去ればいい、などと思っているのだが、そいつは、まだへらへら笑っている。
―だってキミ、倒れてたんだよ。心配するよ。
―別に頼んでない。
あたしは精一杯感じ悪く振る舞っているのに、まるで堪えた様子がない、そいつ。
ばかばかしくなって再び倒れ込んで、乱暴に目を閉じた。
―ほっといて。
目を閉じる直前に見えたのは、そいつの、派手な金髪。
†††
―あ、目、覚めたんだ?
目を開けるとまた金髪がいて、あたしは嫌になってしまうが、さすがにこれ以上眠れない。
見渡すと、今度は知らない部屋にいた。
―どこ、ここ。
金髪はにこりと笑う。
―俺の部屋。キミをほっとくわけにもいかなかったから。
あたしは苛々と、ほっといてと言ったはずだと毒づいた。
太陽の光が降り注いで、とてもとても綺麗なはずなのに、この街はどこかつまらなく見えた。お化粧が剥がれたみたいに。
誰かがあたしを揺すぶっていた。
あたしは正直もう二度と目を開けたくなかったので腹を立てて、ひくうい声で、何、と問う。
その誰かは、ぱっとあたしから手を離し、
―ああ、良かった生きてた!
脳天気ににこにこと笑う。
その陽気さがやけに癇に障って、あたしはますます不機嫌になった。
―余計なこと、しないで。
あたしはいっそ八つ当たり気味に、腹を立ててあたしを罵って自分勝手に立ち去ればいい、などと思っているのだが、そいつは、まだへらへら笑っている。
―だってキミ、倒れてたんだよ。心配するよ。
―別に頼んでない。
あたしは精一杯感じ悪く振る舞っているのに、まるで堪えた様子がない、そいつ。
ばかばかしくなって再び倒れ込んで、乱暴に目を閉じた。
―ほっといて。
目を閉じる直前に見えたのは、そいつの、派手な金髪。
†††
―あ、目、覚めたんだ?
目を開けるとまた金髪がいて、あたしは嫌になってしまうが、さすがにこれ以上眠れない。
見渡すと、今度は知らない部屋にいた。
―どこ、ここ。
金髪はにこりと笑う。
―俺の部屋。キミをほっとくわけにもいかなかったから。
あたしは苛々と、ほっといてと言ったはずだと毒づいた。