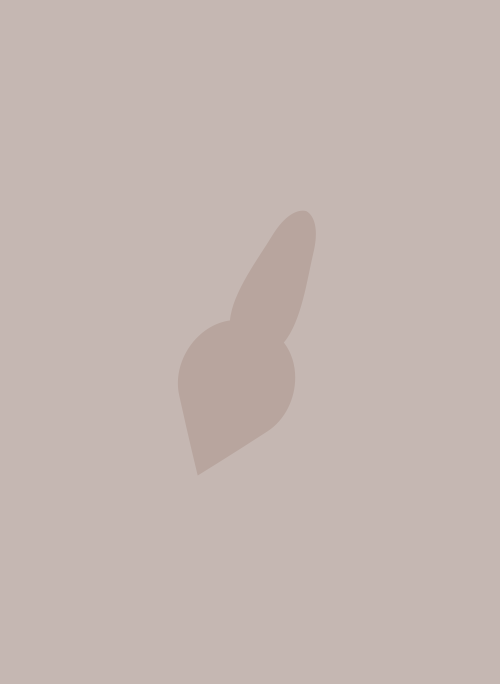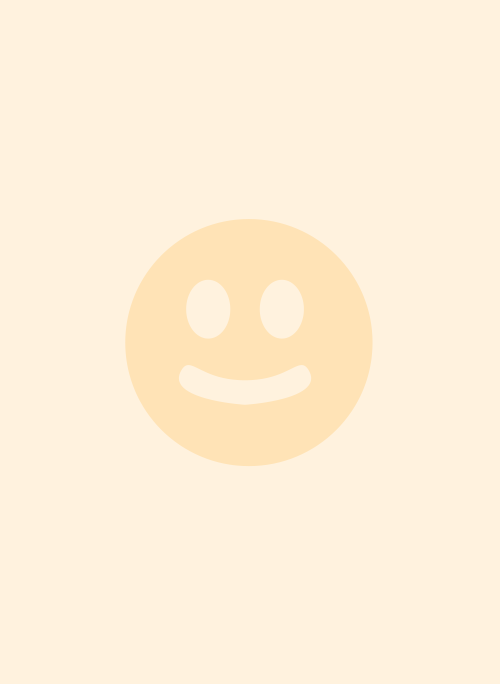ツバメはあたしに綺麗な服を買ってくれた。
あたしにとってはやっぱりおかしいんじゃないかと思うくらい、飾り気のない服だけれど、少なくともカエルの血は付いていない。
―もう、大丈夫。
あたしが微笑むと、ツバメも笑った。
あたしは至極いい気分で、ツバメの煙草を奪ってみる。
案の定煙は喉にしみて、無様に咳込みながら、それをツバメにかえすけど、自分の唇からあの匂いがするのはなかなか素敵。
おかあさまは嫌がるけど、長く帰れないのなら少しくらい構わないはず。
―ねえ、ツバメ。
ツバメがこちらを見た。そういえば、ツバメもあたしが大好きな綺麗なものたちのひとつなのだ。外の世界をたくさん見つめた空色の瞳は、嗜虐心を煽るくらい綺麗。
―いつから煙草を吸っていたっけ。どうして。
ツバメはほそい声で、臭いを消したいから、と答えたきり黙ってしまった。
あたしは間違えたかもしれない。ちらちらとツバメを伺う。
ツバメは哀しみと怒りが混じったような、形容の難しい表情で、あたしを見つめて、それから口を開いた。
―聞け。
そんなことをわざわざ言われなくたって、あたしはツバメの囀りにはきちんと耳を傾けるのだけど、素直に頷いた。
―ここから先は一人だ。
それは、実は予想していた。だってツバメは渡り鳥だもの。あたしはまた、頷く。
それから、ツバメはなぜか痛ましそうな表情をした。あたしが不思議に思っていると、
―お前はもう、帰れない。
あたしにとってはやっぱりおかしいんじゃないかと思うくらい、飾り気のない服だけれど、少なくともカエルの血は付いていない。
―もう、大丈夫。
あたしが微笑むと、ツバメも笑った。
あたしは至極いい気分で、ツバメの煙草を奪ってみる。
案の定煙は喉にしみて、無様に咳込みながら、それをツバメにかえすけど、自分の唇からあの匂いがするのはなかなか素敵。
おかあさまは嫌がるけど、長く帰れないのなら少しくらい構わないはず。
―ねえ、ツバメ。
ツバメがこちらを見た。そういえば、ツバメもあたしが大好きな綺麗なものたちのひとつなのだ。外の世界をたくさん見つめた空色の瞳は、嗜虐心を煽るくらい綺麗。
―いつから煙草を吸っていたっけ。どうして。
ツバメはほそい声で、臭いを消したいから、と答えたきり黙ってしまった。
あたしは間違えたかもしれない。ちらちらとツバメを伺う。
ツバメは哀しみと怒りが混じったような、形容の難しい表情で、あたしを見つめて、それから口を開いた。
―聞け。
そんなことをわざわざ言われなくたって、あたしはツバメの囀りにはきちんと耳を傾けるのだけど、素直に頷いた。
―ここから先は一人だ。
それは、実は予想していた。だってツバメは渡り鳥だもの。あたしはまた、頷く。
それから、ツバメはなぜか痛ましそうな表情をした。あたしが不思議に思っていると、
―お前はもう、帰れない。