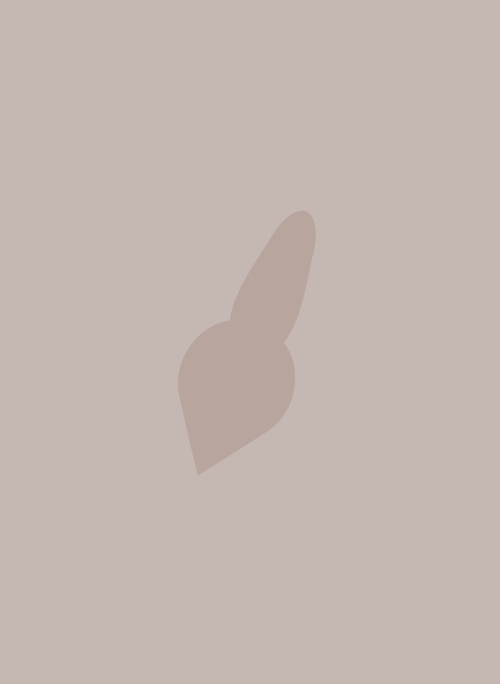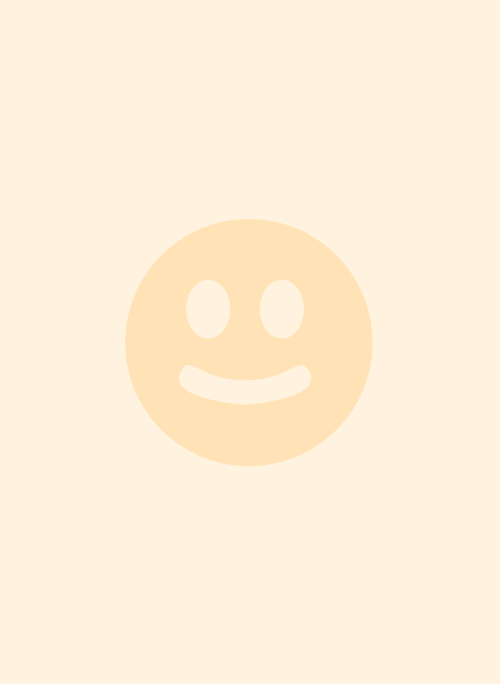「…でも、わからぬのです。どうすればいいか… それに、自分がなぜこれほど動揺しているのかも」
「りいさん」
真鯉がまた、りいを呼んだ。
今度は柔らかい、笑みさえ含んだような声音で。
「やはり…りいさんは真っ直ぐな方ですわ」
「え…?」
真鯉はくすりと笑いをもらした。
「りいさんがいらしてくださって、よかった」
混乱してぱちぱちと瞬きを繰り返すりいに、真鯉は粥を差し出した。
「さあ、冷めてしまう前に、お召し上がりください」
りいは真鯉の思惑がわからず、おずおずと彼女を見た。
真鯉はたおやかに微笑む。
「…召し上がりながら、聞いてくださいませ。…ちょっとした、昔話をいたしましょう」
まだ何が何だかわからないりいをよそに、真鯉はゆっくりと話し始めた。
「今は昔のことでございます。
京に、ある男子(おのこ)が住んでおりました。
位はあまり高くありませんでしたが、穏やかで優しい方でした。
ある日、彼が信太(しのだ)の方へ遠出したときのこと。
山道に、美しい娘が倒れておりました。
彼が駆け寄ると、傷だらけですが、まだ息はあるようでした。
彼は必死に声をかけました。
すると、娘は目を開けて、言いました。
『助けて…!追われているの!!』
それきり、娘はまた気を失ってしまいました。
彼は困りました。
近くには民家はありません。
ですが、娘は見るからに傷だらけで、早く手当てをしなくては命も危ないかもしれません。
迷った末、彼は、馬を飛ばして、娘を連れて帰りました。
傷の手当てをしてやり、娘を部屋に寝かせてやりました」
りいは真鯉の意外に上手い語りに引き込まれて聞いていた。
しかし、その続きは驚くべきものだった。
「りいさん」
真鯉がまた、りいを呼んだ。
今度は柔らかい、笑みさえ含んだような声音で。
「やはり…りいさんは真っ直ぐな方ですわ」
「え…?」
真鯉はくすりと笑いをもらした。
「りいさんがいらしてくださって、よかった」
混乱してぱちぱちと瞬きを繰り返すりいに、真鯉は粥を差し出した。
「さあ、冷めてしまう前に、お召し上がりください」
りいは真鯉の思惑がわからず、おずおずと彼女を見た。
真鯉はたおやかに微笑む。
「…召し上がりながら、聞いてくださいませ。…ちょっとした、昔話をいたしましょう」
まだ何が何だかわからないりいをよそに、真鯉はゆっくりと話し始めた。
「今は昔のことでございます。
京に、ある男子(おのこ)が住んでおりました。
位はあまり高くありませんでしたが、穏やかで優しい方でした。
ある日、彼が信太(しのだ)の方へ遠出したときのこと。
山道に、美しい娘が倒れておりました。
彼が駆け寄ると、傷だらけですが、まだ息はあるようでした。
彼は必死に声をかけました。
すると、娘は目を開けて、言いました。
『助けて…!追われているの!!』
それきり、娘はまた気を失ってしまいました。
彼は困りました。
近くには民家はありません。
ですが、娘は見るからに傷だらけで、早く手当てをしなくては命も危ないかもしれません。
迷った末、彼は、馬を飛ばして、娘を連れて帰りました。
傷の手当てをしてやり、娘を部屋に寝かせてやりました」
りいは真鯉の意外に上手い語りに引き込まれて聞いていた。
しかし、その続きは驚くべきものだった。