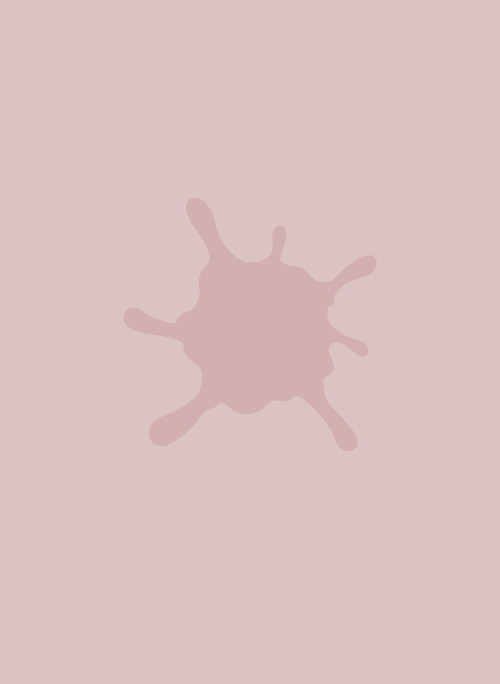この選択が間違っていたと気づくのは、もう少し先だった。
ガラ、
しばらくして、海が教室に入ってくる。
自分の席をみて大きく目を見開いていた。
それを横目でみて内心動揺しながらも遥は気にしないフリをした。
クラスの女子が海を見てクスクスと笑い出す。
「っ・・・。」
海は遥や、クラスの生徒を見ないようにしながら無言で机の上に
鞄をおき、そして床に散らばっている破かれた教科書を集めだした。
海は珍しく泣いていない。
肩が少し震えている。
きっと泣くのを我慢しているのだろう。
「おはよう。」
「おっはよー!冬樹君!」
そして、少し遅れて冬樹が教室に入ってくる。
「何かあったの?」
雰囲気の悪いクラスに気づき、冬樹は男子生徒に問いかける。
すると男子生徒は面白そうに海を指さした。
「・・・海ちゃん?」
「女子がやったらしいぜ?」
冬樹は男子生徒をにらむと、海の方へと歩いていく。
そして黙ってしゃがみ、海と一緒に破れた教科書を拾い始めた。
「海ちゃん、大丈夫?」
「・・・冬樹、くんっ、」
海は、冬樹が自分の味方でいてくれたことが純粋にうれしかった。
堪えていた涙があふれそうになるのを必死で抑えて
震える声で ありがとう と礼を言った。