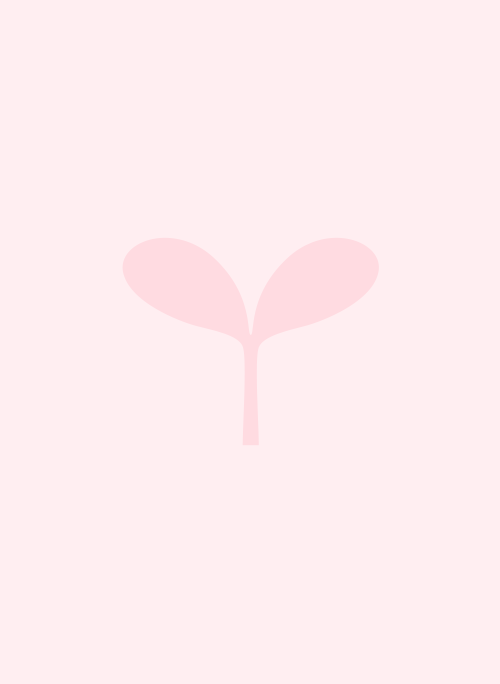ただ、レオニードは根を詰めすぎてしまう節がある。
少しでも早く一人前の薬師になろうとする気持ちは嬉しいが、体を壊してしまえば元も子もない。
みなもは台所へ向かうと、常備してある水出しの茶をコップに入れ、食卓テーブルの上に置いた。
「レオニード、書き終わったら休憩にしよう」
声をかけながら、朝に採ってきた黄色い木苺を皿に盛り、テーブルの中央へ置く。
その間、レオニードからの返事はなかった。
まったく、集中しすぎだよ。……まあ人のことは言えないけれど。
やれやれと肩をすくめながら、みなもはレオニードの横へ回り、人差し指で彼の肩を軽く叩いた。
こちらに気づいてレオニードが動きを止めたところを見計らい、みなもは腰を屈めて顔を近づけ――彼の頬へ優しく口づけた。
驚いたのか、レオニードの肩がわずかに跳ねる。
そして、ようやくペンを置き、苦笑を浮かべながらみなもを見た。
「すまない、気がつかなかった」
いつものことだから気にしていないよと、みなもが切り返そうとした時。
レオニードに謝罪代わりの口づけをされて、唇を塞がれた。
もう何度も繰り返していることなのに慣れない。鼓動も騒ぐ。
未だに夢の中にいるような気がして、当たり前の日々だと思えなかった。
少しでも早く一人前の薬師になろうとする気持ちは嬉しいが、体を壊してしまえば元も子もない。
みなもは台所へ向かうと、常備してある水出しの茶をコップに入れ、食卓テーブルの上に置いた。
「レオニード、書き終わったら休憩にしよう」
声をかけながら、朝に採ってきた黄色い木苺を皿に盛り、テーブルの中央へ置く。
その間、レオニードからの返事はなかった。
まったく、集中しすぎだよ。……まあ人のことは言えないけれど。
やれやれと肩をすくめながら、みなもはレオニードの横へ回り、人差し指で彼の肩を軽く叩いた。
こちらに気づいてレオニードが動きを止めたところを見計らい、みなもは腰を屈めて顔を近づけ――彼の頬へ優しく口づけた。
驚いたのか、レオニードの肩がわずかに跳ねる。
そして、ようやくペンを置き、苦笑を浮かべながらみなもを見た。
「すまない、気がつかなかった」
いつものことだから気にしていないよと、みなもが切り返そうとした時。
レオニードに謝罪代わりの口づけをされて、唇を塞がれた。
もう何度も繰り返していることなのに慣れない。鼓動も騒ぐ。
未だに夢の中にいるような気がして、当たり前の日々だと思えなかった。