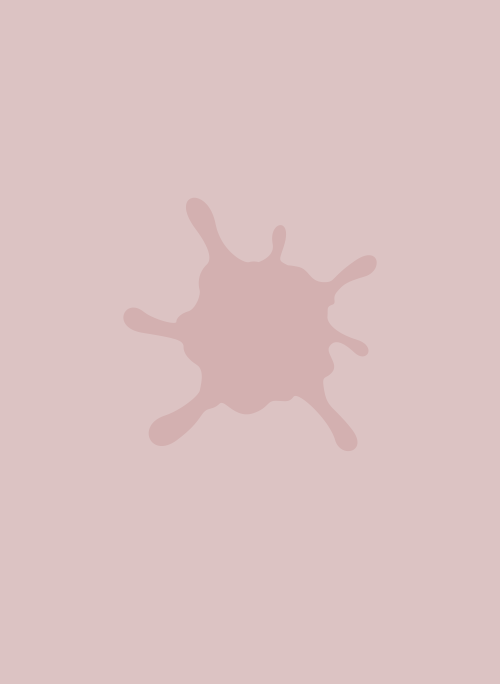「どうしてそんな無理をさせた!」
「もう…止められなかった。あんなに楽しみにしていたんだ。たった一度だけ叶えられるかもしれない、たった一度だけでもいいから、やらせたかった…」
「結果、これかよ…こんな…」
なにもかも、冷たかった。
くすんだストラト、
くしゃくしゃの楽譜、
雨に濡れた肌、それ以上に、
消えていく彼女の温もり。
僕は彼女の兄に取り返しのつかない現実を
責められた。
雨足がさらに鳴り響く。
いつまでも呆然としていた、
僕をそっちのけで、
泣きわめいていた。
彼女は、覚悟していたのだろうか?
こうなることがわかっていたのだろうか?
こんな風景を見せるんだって、
でもその先の光景まで、
考えているわけはないか…。
「早く出ていけ…」
「…」
「思い出と引き換えに命を奪いやがった、お前らの青春は汚れちまってる!」
「…」
「ああ、せいぜい後悔してやってくれよ」
僕は動けなかった。
やがて、引きずり出されて部屋を後にした。
†
ライブ会場は彼女が死んだ事実を知らないまま、
クライマックスを迎えていた。
たった一曲、ステージから鳴り響いた、
あの瞬間は彼女の兄が言うように、
青春という綺麗なフレームに
やがて黄ばんで消えていくだけで、
あの瞬間、あの歓声は、
藻屑のように掻き消されていた。
僕はそれを思ったときに、
初めて空しさと、
勢いの気持ちを呪った。
壁にもたれかけ、轟音に頭傾けて
泣き叫んだ。
エレクトロリックサーカスが聞こえる。
君はあの歌のように散っていった。
澄み切った色のその先へ。
†
僕たちに明日はなかった。
僕はまだわからない。
残された鳥は、
灰色の空を舞う、
そんな現実が、
残されたもの。
「花は咲いたんだ。たった一度、芽吹いたんだ」
夜は明け、皆がそれぞれに散る。
僕は知らぬ世界へ、道しるべも無しに
飛び出していく。
そうだ。
愛に応える術を見失ったままで、
僕は歩きだした。
「もう…止められなかった。あんなに楽しみにしていたんだ。たった一度だけ叶えられるかもしれない、たった一度だけでもいいから、やらせたかった…」
「結果、これかよ…こんな…」
なにもかも、冷たかった。
くすんだストラト、
くしゃくしゃの楽譜、
雨に濡れた肌、それ以上に、
消えていく彼女の温もり。
僕は彼女の兄に取り返しのつかない現実を
責められた。
雨足がさらに鳴り響く。
いつまでも呆然としていた、
僕をそっちのけで、
泣きわめいていた。
彼女は、覚悟していたのだろうか?
こうなることがわかっていたのだろうか?
こんな風景を見せるんだって、
でもその先の光景まで、
考えているわけはないか…。
「早く出ていけ…」
「…」
「思い出と引き換えに命を奪いやがった、お前らの青春は汚れちまってる!」
「…」
「ああ、せいぜい後悔してやってくれよ」
僕は動けなかった。
やがて、引きずり出されて部屋を後にした。
†
ライブ会場は彼女が死んだ事実を知らないまま、
クライマックスを迎えていた。
たった一曲、ステージから鳴り響いた、
あの瞬間は彼女の兄が言うように、
青春という綺麗なフレームに
やがて黄ばんで消えていくだけで、
あの瞬間、あの歓声は、
藻屑のように掻き消されていた。
僕はそれを思ったときに、
初めて空しさと、
勢いの気持ちを呪った。
壁にもたれかけ、轟音に頭傾けて
泣き叫んだ。
エレクトロリックサーカスが聞こえる。
君はあの歌のように散っていった。
澄み切った色のその先へ。
†
僕たちに明日はなかった。
僕はまだわからない。
残された鳥は、
灰色の空を舞う、
そんな現実が、
残されたもの。
「花は咲いたんだ。たった一度、芽吹いたんだ」
夜は明け、皆がそれぞれに散る。
僕は知らぬ世界へ、道しるべも無しに
飛び出していく。
そうだ。
愛に応える術を見失ったままで、
僕は歩きだした。