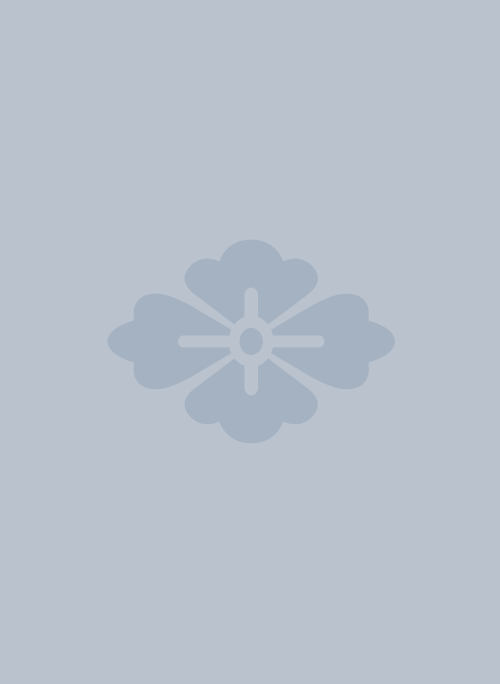小さくて、やわらかい。
保護欲と、征服欲を満たしてくれる。
可愛い女の子を抱きしめるよりも。
でっかくて、あったかく。
ともすると、めちゃくちゃに壊し兼ねないほど。
ハニーは強く、激しく僕を求めてくる。
そんな熱に巻き込まれることが、心地良かったんだ。
………。
……その、熱の元の手が、今。
ベッドに仰向けになり、ハニーを見つめる僕の。
右頬から、あごにかけての全部を、包み込む。
それと一緒に。
今まで立っていたハニーが、ぎしり、と音を鳴らして。
僕の寝ているベッドに腰を下ろした。
と。
緑色の瞳が、ゆっくりと近づいて来て。
僕の唇に、ハニーの唇が軽く触れた。
「……酒のにおいがする。
私に黙って飲んだろう……?」
「……う」
指された言葉に、声を失えば。
ハニーはもう一度、僕に口付けて、ささやいた。
「……莫迦なことを……相当、苦しんだんじゃないか?」
「それは……っ!
ハニーが、嫌酒剤なんて、飲ませるからっ!」
今なお、力が今ひとつはいらず。
起き上がればぐらぐらすることは、必須の自分のカラダを抱えて、ささやき返せば。
ハニーは、クビを振った。
「……まさか。
酒を本格的に飲まなくても。
奈良漬け程度のわずかなアルコール分を摂取するだけで苦しむ薬を。
私が、大事な螢にこっそり飲ませたまま、黙って。
どこかに出かけるワケが無い」
「……じゃあ、なんで……」
こんなことになったのか?
腑に落ちない僕に、ハニーは、目を伏せた。
保護欲と、征服欲を満たしてくれる。
可愛い女の子を抱きしめるよりも。
でっかくて、あったかく。
ともすると、めちゃくちゃに壊し兼ねないほど。
ハニーは強く、激しく僕を求めてくる。
そんな熱に巻き込まれることが、心地良かったんだ。
………。
……その、熱の元の手が、今。
ベッドに仰向けになり、ハニーを見つめる僕の。
右頬から、あごにかけての全部を、包み込む。
それと一緒に。
今まで立っていたハニーが、ぎしり、と音を鳴らして。
僕の寝ているベッドに腰を下ろした。
と。
緑色の瞳が、ゆっくりと近づいて来て。
僕の唇に、ハニーの唇が軽く触れた。
「……酒のにおいがする。
私に黙って飲んだろう……?」
「……う」
指された言葉に、声を失えば。
ハニーはもう一度、僕に口付けて、ささやいた。
「……莫迦なことを……相当、苦しんだんじゃないか?」
「それは……っ!
ハニーが、嫌酒剤なんて、飲ませるからっ!」
今なお、力が今ひとつはいらず。
起き上がればぐらぐらすることは、必須の自分のカラダを抱えて、ささやき返せば。
ハニーは、クビを振った。
「……まさか。
酒を本格的に飲まなくても。
奈良漬け程度のわずかなアルコール分を摂取するだけで苦しむ薬を。
私が、大事な螢にこっそり飲ませたまま、黙って。
どこかに出かけるワケが無い」
「……じゃあ、なんで……」
こんなことになったのか?
腑に落ちない僕に、ハニーは、目を伏せた。