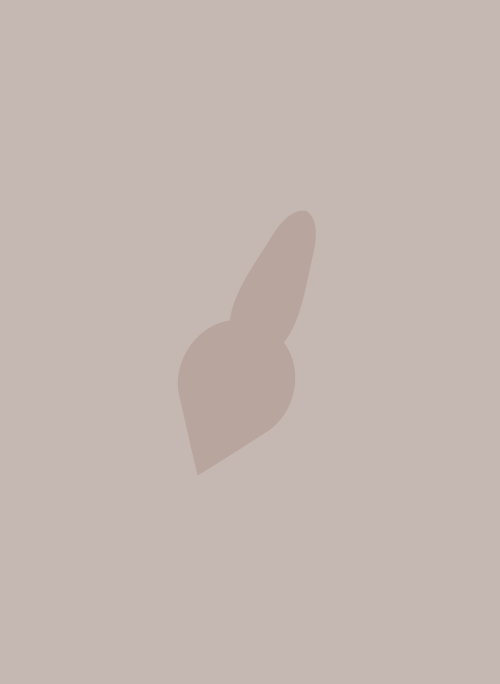―――…
「サラちゃん!」
10分ほど歩いて到着した温泉の駐車場で、あたしを呼び止めたのは大崎くんだった。
「大崎くん!うわー、遅いね!びっくり。」
「あぁ、ちょっとゆっくりしちゃって。―――… 貸切(風呂)、行く?いま、俺が入ったとこだから、空いてるよ。」
「ほんと!?やった、ラッキー!!」
大崎くんはチャリン、とあたしの掌に鍵を落とす。
「10番のとこ。受付には、鍵は明日返しますって俺から言っとくから、ゆっくり入っといでよ。寒いだろ。」
「ほんと?… じゃ、お言葉に甘えようかな、ありがと!」
――…かくして、哀れな羊は罠にかかる。
甘い、罠に。
このとき、遠ざかっていく大崎くんが背中の向こうで微笑みを浮かべていたのを、あたしは知らなかった。
この扉の向こうに何があるのか… 知る由もなかった。