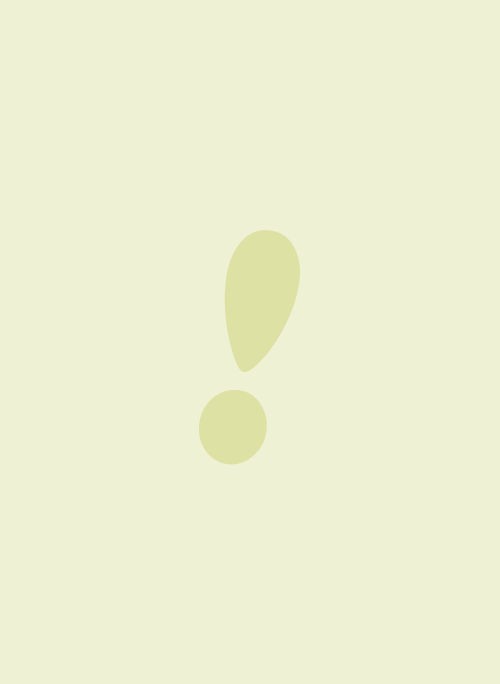「おい、何してんだよ」
ヤン…?
「いや、別に」
ヤンは中指を立てて言った。
「ファッキン・ルーザー・サノバビッチ。お前、女にセクハラしすぎ。その子は気づいてないけど、『これはアメリカの文化』とか言って、女の腰を触ったりしすぎ。誰でもセクハラだと思うよ。」
「なんだと?!白人種の俺が、お前みたいなイエローモンキーに負けるとでも、思ってんのか?!」
「そのイエローモンキーを犯そうとしてる、お前には勝てると思うけどな。」
「くぅ…っ」
「言い返せないのか?このマザーファッカー。お前なんか、一生、×××でもしておけ」
いつもと変わらない、無機質な顔で、淡々とファックファック言ってるのが、信じられなかった。
それと、何で、ここにヤンがいたのかも信じられなかった。
「何だと?!殴ってやるっ!」
とその白人さんが殴ろうとしたとき、ヤンはケータイを持ち出した。
「もしもし、警察ですか?ここにぺドファイル(日本語で言う、ロリコン)がいます。助けてください。キャー助けてーファッキン・アグリー・ファッカーに犯されるー、ファッカーなだけに(棒読み)」
(解説:本来、ファック(fuck)は犯すとか性交と言う意味らしいです。ファックにERをつけたら、ファッカー(fucker)=犯す人とも言えますし、愚かな野朗とも言えますので、ファッキン・アグリー・ファッカーは“ブサイクな愚か者のクソッタレ”とも訳せますし“性交してる不細工な犯す人”とも訳せます。)
その白人さんは逃げて行った。
「あ、ありがとう…ヤン」
「どういたしまして。立てる?」
と言って、手を差し伸べてくれた。
「さて、このコトをオフィスの人に言うよ」
アタシは動揺してるのに、ヤンは動揺してなかった。ってゆーか、かなり冷静だった。
アタシはポロポロと涙が今になって出てきた。
「ごめん、止まらない…」
アタシが泣いてるとヤンは誰にも見せたことの無い顔を見せてくれた。
「泣かれると困るんだけど、その時は、どうすればいい?」
「頭、撫でて?」
何でアタシ、こんなコト頼んでるんだろう…
ヤン…?
「いや、別に」
ヤンは中指を立てて言った。
「ファッキン・ルーザー・サノバビッチ。お前、女にセクハラしすぎ。その子は気づいてないけど、『これはアメリカの文化』とか言って、女の腰を触ったりしすぎ。誰でもセクハラだと思うよ。」
「なんだと?!白人種の俺が、お前みたいなイエローモンキーに負けるとでも、思ってんのか?!」
「そのイエローモンキーを犯そうとしてる、お前には勝てると思うけどな。」
「くぅ…っ」
「言い返せないのか?このマザーファッカー。お前なんか、一生、×××でもしておけ」
いつもと変わらない、無機質な顔で、淡々とファックファック言ってるのが、信じられなかった。
それと、何で、ここにヤンがいたのかも信じられなかった。
「何だと?!殴ってやるっ!」
とその白人さんが殴ろうとしたとき、ヤンはケータイを持ち出した。
「もしもし、警察ですか?ここにぺドファイル(日本語で言う、ロリコン)がいます。助けてください。キャー助けてーファッキン・アグリー・ファッカーに犯されるー、ファッカーなだけに(棒読み)」
(解説:本来、ファック(fuck)は犯すとか性交と言う意味らしいです。ファックにERをつけたら、ファッカー(fucker)=犯す人とも言えますし、愚かな野朗とも言えますので、ファッキン・アグリー・ファッカーは“ブサイクな愚か者のクソッタレ”とも訳せますし“性交してる不細工な犯す人”とも訳せます。)
その白人さんは逃げて行った。
「あ、ありがとう…ヤン」
「どういたしまして。立てる?」
と言って、手を差し伸べてくれた。
「さて、このコトをオフィスの人に言うよ」
アタシは動揺してるのに、ヤンは動揺してなかった。ってゆーか、かなり冷静だった。
アタシはポロポロと涙が今になって出てきた。
「ごめん、止まらない…」
アタシが泣いてるとヤンは誰にも見せたことの無い顔を見せてくれた。
「泣かれると困るんだけど、その時は、どうすればいい?」
「頭、撫でて?」
何でアタシ、こんなコト頼んでるんだろう…