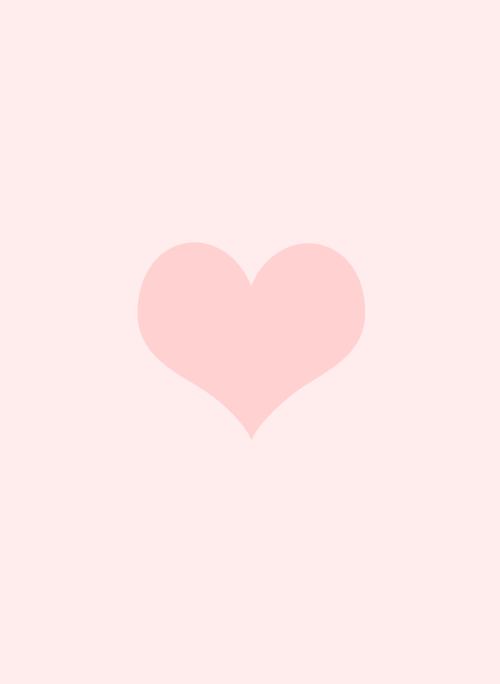「みちるさん、さっきはなんで俺を見てたの?なにか顔についてた…」
「いや…。その…き綺麗だなあて…」
「綺麗…俺が…、何もしてないよ。」
りんご飴を食べながら呟く
祭りの会場から移動して
小さな公園にあたし達はいた
「何もしてなくても。色気っていうのかな…そんな感じの…うん。多分、」
「…そういえば監督も似たようなこと言ってたな。なんか…綺麗に見えるようになったとか何とか…」
監督も気づいてたんだ…
本人にはわからない
だろう魅力というやつ…
自然と…
人が振り向くような雰囲気
それは凡人にはない
選ばれた人間にあらかじめ
備わっているモノ
皮肉にも彼の父
神田怜一の持っていたもの
彼は気付いてはない…
とてもきれいな華… みたいな
誰もが目をとめるような
「……色気ねぇ。まぁあるに越したコトないけどな、んな沢山ばらまくものじゃないな。芝居は別としてさ…」
「うん…」
「…俺が今更別の女を誘惑するわけないだろ。」
耳元で囁く声にドキドキした
りんご飴は食べかけのまま握ってる
「…翔太く…」
「…呼び捨てで呼べばいいのに。」
「だってばれるのが…」