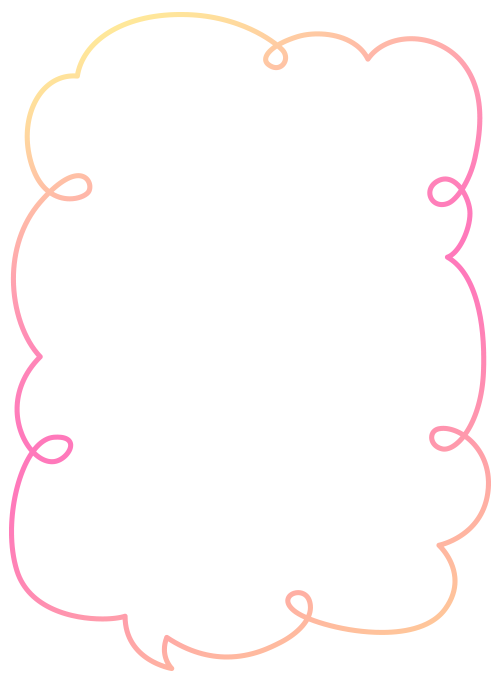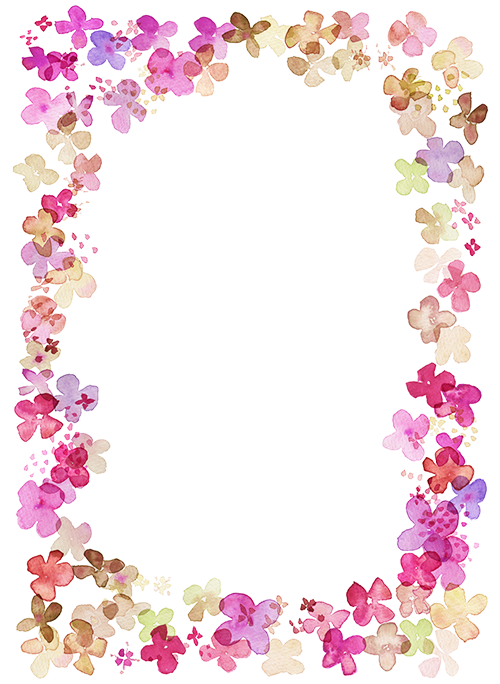「理子は多分、紫苑君と出会って変われたんだ」
洗い終わった皿をお母さんに渡しながら微笑む理子。
こういうの……いいな。
目の前には、ずっと俺が望んでいた家族の温もりが溢れていて。
「昨日は理子とケンカでもしたのかい?久しぶりに帰ってきたと思ったら、ずいぶん落ち込んでいたようだから」
「俺が悪いんです……――」
なぜだか自分でも分からない。
でも、不思議と口から零れ落ちた言葉。
自分の過去、それに家庭環境。
そんな話をされても理子のお父さんは困惑するだけ。
俺に幻滅することはあっても喜ぶことはない。
頭では分かっているのに、俺は話し続けた。
同情をしてほしいわけでも、慰めてほしいわけでもない。
ただ、全てを正直に話した。