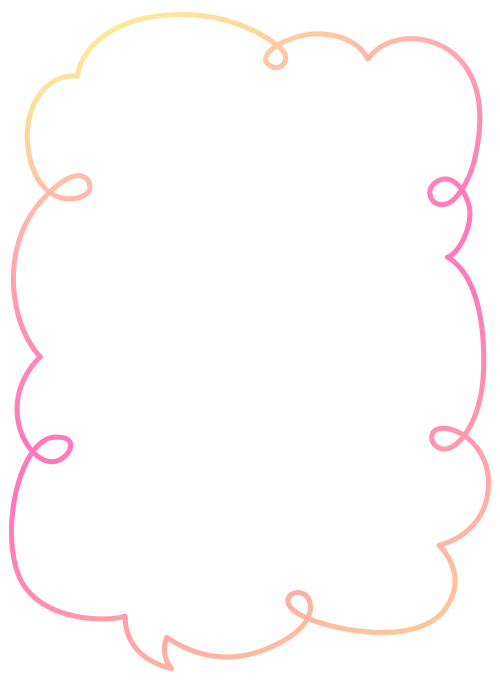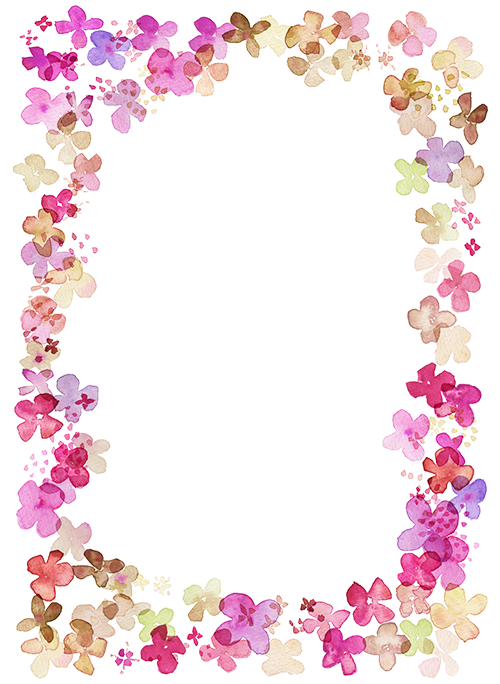指先は首筋から徐々に下に移動する。
「っ……」
鎖骨に彼の指先が触れたとき、息が止まりそうになった。
本当ならすぐにでもその手を振りはらわなきゃいけない。
それなのに、体が……
それに心がいうことを聞いてくれない。
思わずゴクリと唾を飲み込むと、紫苑の指がスッと離れた。
「嫌な時は、抵抗しないと」
紫苑はフッと笑って「またね」と言ってあたしの頭を撫でた。
大きな手の平が体のどこかに触れる度に、その部分が敏感になる。
全身がゾクゾクして、不思議な感覚が込み上げる。
あたし……もしかして……。
この時、あたしは自分の気持ちをようやく悟った。
あたし……紫苑のことが……――。
「今度はキス、しようね?」
そんな甘い言葉を残して、紫苑は屋上から出ていった。