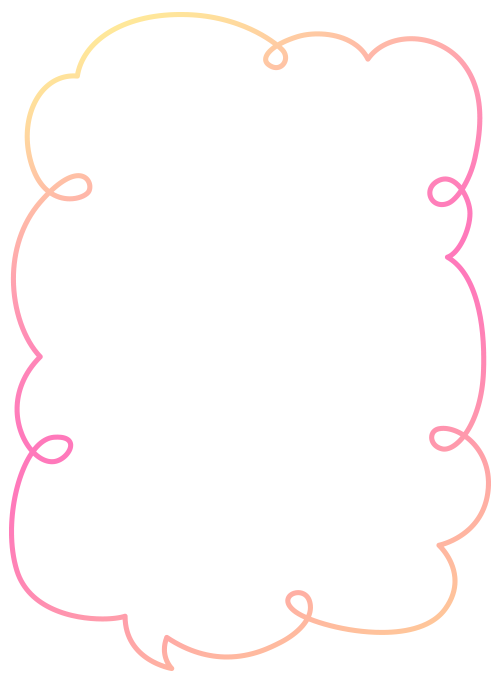「さっき金の無心したのって、この子が原因?いつまでも私に頼らないで」
甘ったるい香水の匂いが鼻について、思わず女性を凝視する。
この人……、どこかで見たような気がする。
紫苑が『母さん』と呼んだ女性は、ブランドもののバッグから茶色い封筒を取り出した。
「俺がいつあんたに頼った?」
「親に向かってその態度はなによ」
「親なら親らしいことの一つくらいすれば?」
紫苑の声がいつもより低くて。目は恐ろしいほどに冷たい。
「知ったような口、聞かないでちょうだい!!」
その言葉と同時にパシンッという乾いた音が辺りに響いた。