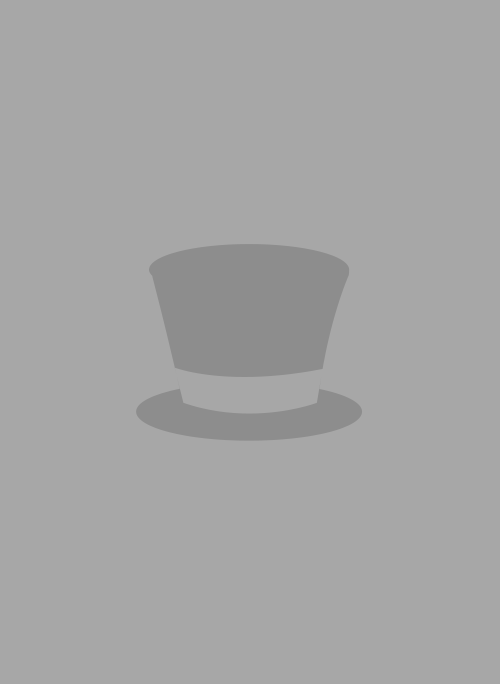「すごい夢を持っているのですね。
僕は考えた事もなかった。」
そう、リュウは国体なんていうのは大人の世界だと思っていた。
それに、リュウにとってテニスは、
学校でするものだった。
「まあな。
なんだかリュウのことを考えると出来そうな気がする。
ここだけの話だが、山崎だと…
確かにあいつは上手いが、
ダブルスでは無理な気がする。
あいつが出たければシングルで出れば良いさ。
リュウと組めば、
俺にお前を守ろうとする不思議な力が芽生えそうな気がしているんだ。
笑うなよ。
だから実力以上のものが出る。
だからな、こんな所でふらふらするより、
俺の夢を叶えさせるために、
お前は体力の消耗が激しいから、
家に帰って体を休めて、
まあ自己管理を考えて行動してくれ。
今日は店が忙しかったから配達を手伝ったが、
普段は一応猛勉強をしているのだぞ。
これでも俺は3年だからな。」
「ふーん、先輩って大変なんですね。」
水嶋が自分の事を心配してそんな事を… と思った。
しばらくして見送られる形で駅に向った。
「先輩、アレ。」
二人が駅に近づいた時だった。
横丁の路地で誰かがうずくまっているのが見えた。
「外人さんかなあ。
酔っぱらって気分でも悪いのか…
交番に知らせるか。
それともちょっと様子を見ようか。」
そう言いながら水嶋は近づいている。
リュウも後をついた。
「この人… カイル・ハワードだ。」
顔を見た水嶋、
驚いたような声を出した。
「先輩の知り合いですか。」
「いや、知り合いってほどじゃあないけど、
ここ数日、うちの店をひいきにしてくれて…
日本語の達者なアメリカ人。
確か、ビジネスで日本に来ているとか言っていた。
宿もこの近くのはずだ。
高級なシティホテルだったぞ。
親父が,あそこなら寿司屋も日本料理店も揃っているのに、
わざわざ来てくれて嬉しいねえ、なんて言っていたから…
電話で聞いてみる。」
そう言いながら水嶋は携帯を出した。