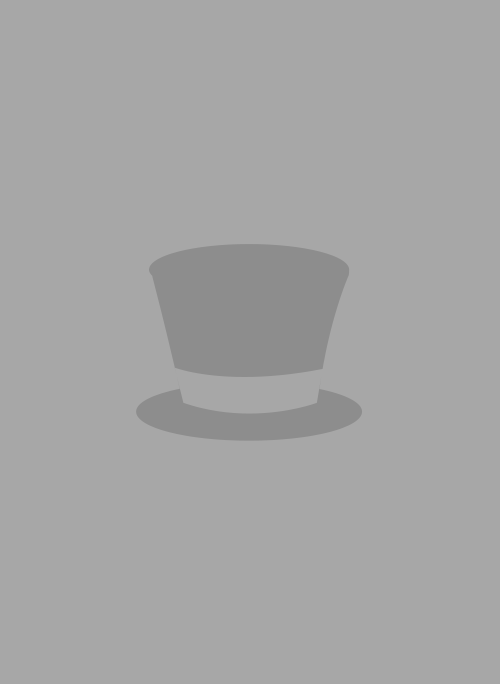自分はこれほどにカイルの存在を頼りにしているが、
果たして父は…
リュウは一度も父の口からカイルの事を…
いや、そう言えばソフィアの事だって…
一度だけ、これが出生証明書、名前はソフィア、
と言って見せてもらっただけだ。
父はどんな気持ちで生きてきたのだろう。
カイルの事は知らなかったのかも知れない。
ソフィアの事だって…
再婚したぐらいだから忘れているのかも知れない。
だから、どんな人なのか… 何も分らなかった。
僕と父さんは、肝心な、大切な話はして来なかった。
そうじゃあない。
きっと、僕が成長していなかったのだ。
初めから父さんしかいなかったから、
それが当たり前の暮らし、と思っていた。
僕が周りを見なかったのだ。
だから父さんは話せなかった。
父さんは僕に、
わざわざ死んだ人を思い出させ、
寂しがらせたくは無かったのだ。
中学になったらあいつらが入って来て…
ますます話をする機会が少なくなった。
早く父さんが起きて…
いろいろな話を聞きたい。
その夜も…
そんなことが走馬灯のようにリュウの頭を過ぎり…
寝たふりはしていたが、
看護師さんが見回り、
警備員が廊下を3度巡回しているのも覚えている。
しかし、翌朝の気分は悪いものではなかった。
それどころか、
携帯電話にカイルの番号がある、
というだけで温かい気持ちになっていた。