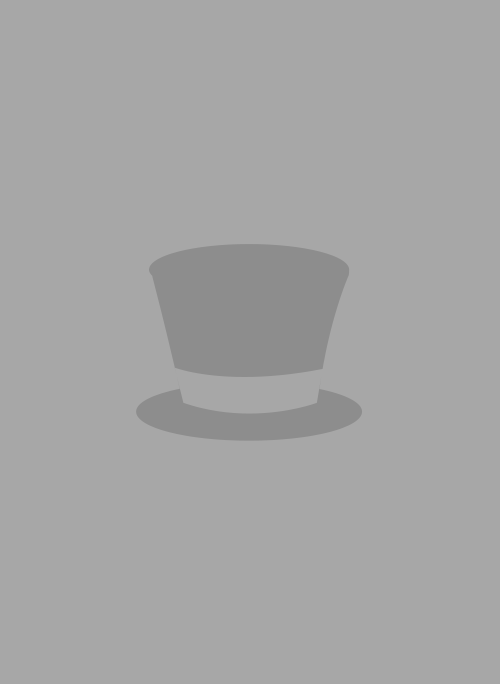「帰って、かばんやラケットは置いてきました。」
それは確かにそうなるから嘘ではない。
「じゃあ、今からどこへ行こうとしていたんだ。」
「だから… ただぶらぶらと… 散歩です。
僕、こんな様子は初めてだから。」
「分かった。俺が案内してやる。
この桶を戻してくるから…
あ、一緒に来い。
親父に寿司を握ってもらおう。」
「いえ、今、食べたところですから。」
「そうか。じゃあ、外で待っていてくれ。」
「なあ、リュウ、
これから始まる地区予選、頑張るぞ。
そのまま調子を上げていき…
夏の全国大会で優勝したい。
俺たち3年には最後の試合だからな。
優勝するには2年生だが、
お前と山崎に頑張ってもらいたい。
山崎はプロを目指しているらしいから…
きっと今頃も、
所属しているテニススクールで頑張っているだろう。」
「山崎が… 知らなかった。」
「まあ、お前はそう言うことにあまり関心を示さないからな。
お前以外は皆知っているぞ。
夏が終わればお前たちが主役だ。
俺な、最後に国体に出たいんだ。
少年の部っているのがあるだろ。
それに東京代表として出たい。
なあ、その時、俺とダブルスを組まないか。」
いきなり、水嶋は
リュウが考えた事もない言葉を出してきた。
こうして2人で夜の街を歩きながら話していて、
思わず本心が出たようだ。
「僕が先輩と… 」
「ああ、勿論それには地区大会や全国大会で優勝するか、
少なくとも俺たちは負け無し、
で進まないと認められないが…
この間先生が、見込みはある、と言ってくれた。
秋になれば、他の3年生は受験勉強に入るだろうが、
俺は最後までやりたいと思っている。
大学生や社会人も出場しているが…
その中で実力を発揮して、
東京にダブルスの優勝旗を持ち帰り、
俺たちは優勝カップ、って言うのはどうだ。」