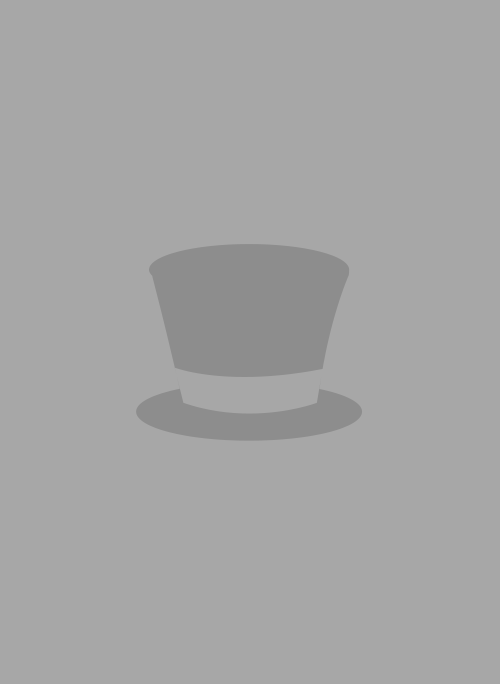「それで、こんな時間に何でしょう。
何か分かったのですか。」
看護師が出て行くと、リュウは刑事に話しかけた。
「ええ、毒チョコレートを送った犯人は
アメリカ人のナタリー・ミューズ、60歳でした。
お知り合いですか。」
「いえ、知りません。」
「60歳と言うならばお父さんと同年齢、
お父さんから聞いたことはありませんか。」
どうやら刑事たちは、
リュウの顔立ちがハーフ的、ということで
何か関係があったのでは、と思っているようだった。
「あの、差障りなければ、お母さんについて… 」
もう一人の刑事が声を出した。
「僕の母はソフィアと言います。
僕がまだおなかにいる時に交通事故で死にました。
父がアメリカの大学で教えていた時です。
だから僕は未熟児で生まれ…
今はこうして大きくなりましたが、
中学までは小さかったです。
だけど、今頃になって、
そのチョコレートを送った人が何か関係があると言うわけですか。
未熟児だったから退院出きるまで1年ぐらいかかったようですが、
それからは日本に帰り…
ずっと父と2人で暮らしてきました。
刑事さんたちは僕がこんな顔つきで、
犯人が外国人だったと言う事で、
16年前からのトラブルが原因と言うのですか。
そう思っているのなら僕は何も分からないから、
父が寝覚めてから聞いてください。
母の思い出もありませんから。」
そう言って、リュウは無表情になり、
刑事たちを無視する態度をあからさまにした。
自分の風貌で、
外国人という犯人に結びつけた警察…
無性に腹が立っていた。
もう話をする気は無い、と言う顔をしたリュウだ。
「いえ、そんなつもりでは… 」
刑事たちはそのリュウの態度に慌てた。
自分たちでも、そんな昔のことを詮索するつもりはなかったが…
リュウを見ていて、つい言葉が出てしまった。