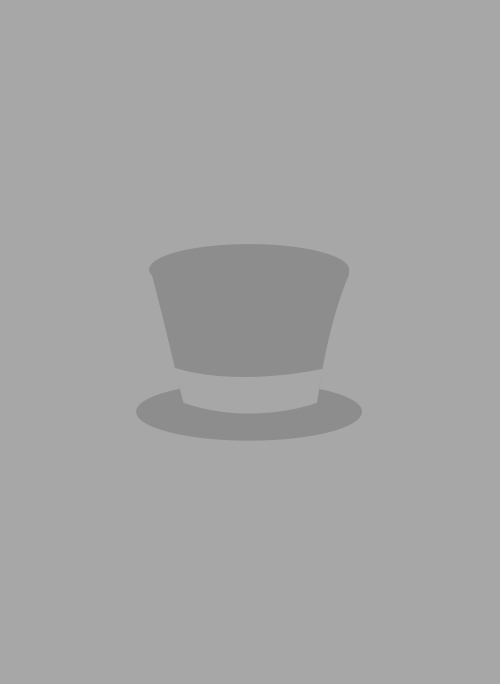水嶋はリュウのために握り飯とおかずを持って来てくれたが、
それは昼食の弁当にする事にして、
一緒にホテルのモーニングを口にしている。
「お前、今朝早くにお袋さんが来たぞ。
まだ眠っていると言って、
俺が着替えを受け取っておいたが…
昨日は親父さんが留守だったんだってな。
それでお前、帰りたくなかったのか。
お袋さん、気にしていたぞ。
まあ、アレだけ若いと嫌かも知れないが…
お前、もう4年になるのに妹たちと口を利かないんだってな。
そんなに嫌いなのか。」
「先輩、そんな話は朝食に相応しくない。
カイルの分かる話にしようよ。」
リュウは水嶋の話をさえぎった。
「カイル… お前、もうそんなに。」
「私たちは大抵名前で呼び合っています。
彼はリュウ、私はカイル。
君はなんと言う名前ですか。」
痛み止めを飲んでいるからか、
カイルは普通に話している。
「あ、僕は水嶋健史です。
じゃあ、タケシと呼んでください。」
「分かった。
タケシはあのすし屋の息子だったね。
二人とも同じ学校。」
「ええ、僕のほうがリュウより1歳上でテニスも先輩だから、
リュウは僕の事を先輩、って呼んでいます。
こいつ、おとなしいのか我がままなのか分からないような…
なんか目が離せないところがあり…
でも、テニスの才能はすごいですよ。
まあ、僕にとっては可愛い弟のような存在なのです。」
そう言いながら、
水嶋は口いっぱいに
ベーコンエッグを頬張っている。
身長は同じぐらいだが、
3年でテニス部の部長をしている
水嶋の方ががっちりして落ち着き感がある。
が、この食べ方は…
いつも店の残り物を食べているのか、
久しぶりに食べた洋風の朝食…
美味い、を体中で表している。
「先輩、お待たせしました。
カイル、気をつけて。
またどこかで会えたら良いですね。
さようなら。」