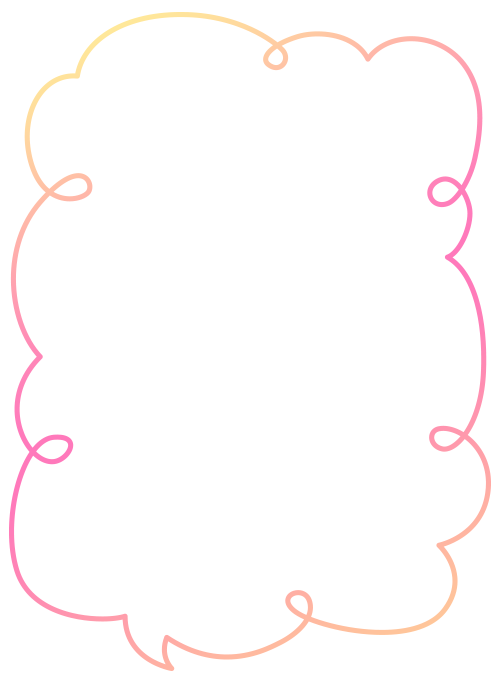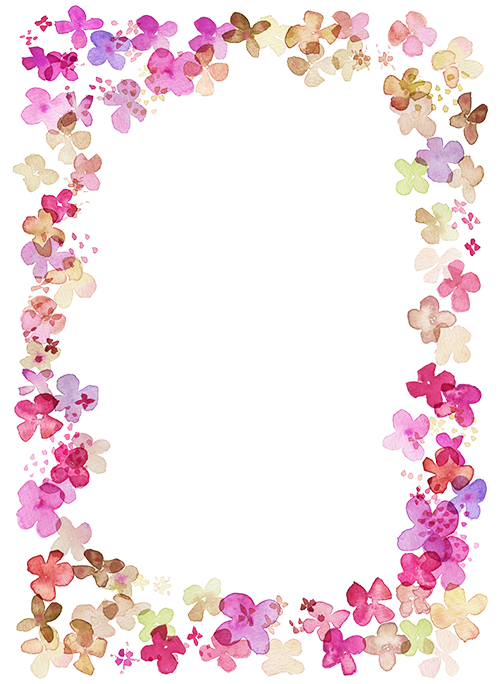「これ、家の鍵。勝手に入って大丈夫だから」
一哉と入れ替わるように教室に入ってきた大知はあたしに銀色の小さな鍵を手渡した。
その小さな鍵は手の平にずっしりと重たく圧し掛かる。
「分かった。でも今日だけだよ?あたし彼氏が……――」
「知ってる。唯を頼むな」
大知はそれだけ言うと、足早に教室から出て行った。
大知の背中を一哉に重ね合わせると、嘘を吐いてしまった事への罪悪感が増した気がした。
一哉と入れ替わるように教室に入ってきた大知はあたしに銀色の小さな鍵を手渡した。
その小さな鍵は手の平にずっしりと重たく圧し掛かる。
「分かった。でも今日だけだよ?あたし彼氏が……――」
「知ってる。唯を頼むな」
大知はそれだけ言うと、足早に教室から出て行った。
大知の背中を一哉に重ね合わせると、嘘を吐いてしまった事への罪悪感が増した気がした。