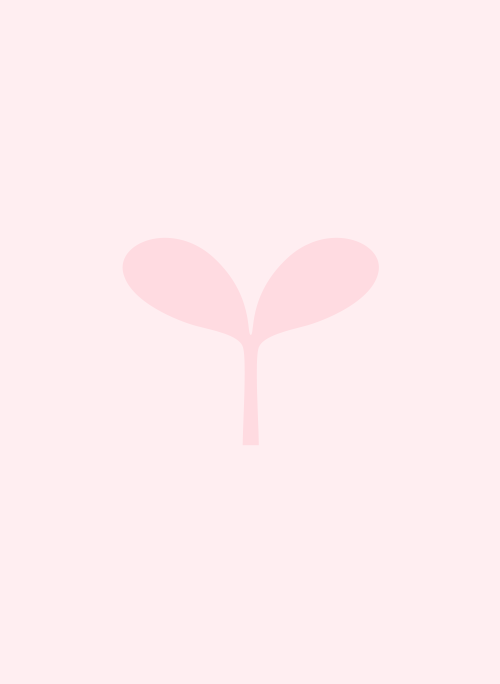濡れた手を拭き、彼はそっと彼女の髪を撫で、口を開けた。
「リオル、僕は……君を彼女と重ねたい訳じゃない。だから、勘違いしないでおくれ」
その言葉に、リオルの瞳から、涙が零れ落ちる。
けれどそれは嬉しさからではなく、悲しさから。
「じゃあ私は何のために、拾われたのですか」
主の世話係をする訳でもなければ、彼の心に空いた穴を埋める訳でもない。
そんな奴隷、必要ない。
存在する意味なんて、ない。
「何の役にも立たない奴隷なんて――」
刹那、温もりが、彼女を包み込む。
「リオル、お願いだから、そんな言い方しないでおくれ」
悲しそうな声が、耳元でした。
「僕は君を奴隷として拾ったわけじゃない。確かに、僕はシンデレラに惹かれていた。けれどだからと言って、彼女と重ねるために拾ったわけでもない」
少し、彼女を抱きしめる腕に力が入る。
「ただ君を、助けたかっただけなんだ」
奴隷だから、という考えをするのは、やめてほしい。
けれどそれは生まれながらそういう環境で育ってきた彼女に理解してもらうのは、難しいだろう。
「君には奴隷ではなく、一人の人間として、生きてほしい」
けれどその烙印がある限り、奴隷という言葉が彼女の中から消えるのは難しいから、だから僕は、必ず彼に――兄に、魔法を解かせる。