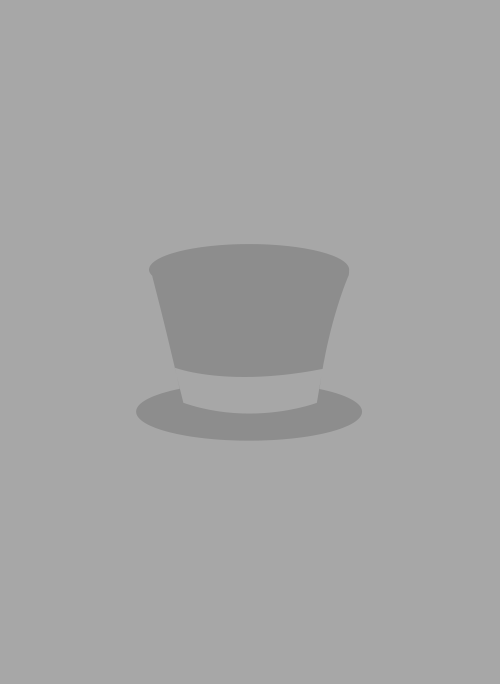「孝史、もう十分だわ。
帰りましょう。」
今度は、かおるがそう言ってバッグを掴んだ。
「お姉ちゃん、何を言っているのだよ。
父さんに会えたのだよ。
これで僕たちは施設に行かなくても良いんだよ。
父さん、僕たちここで暮らせるのでしょ。」
「ああ、しかし…
施設って… 君たちにはお母さんがいるのだろ。
私が離婚したと言う人に聞かなくても良いのか。」
本当に何も知らないように、
柳井は不確かな言葉を出した。
記憶もないし、知らないのなら教えなくては、と
孝史は好意的な気持ちから説明を始めた。
「母さんは死んだ。
だから僕たちは身寄りが無いと言う事で養護施設へ行かなくてはならなかった。
でも、あそこは嫌いだったから出て来たんだ。
こうして父さんに会えて嬉しいと思っているけど…
父さんが僕たち以外の子供を連れていたから、
お姉ちゃんは戸惑っているんだよ。
僕は構わないよ。
この子、すごく可愛いから、
僕が可愛がってやるよ。」
孝史はそう言いながら、
父の後ろで隠れるようにして立っている鳶人を見て、
優しい目で微笑んでいる。
その孝史の眼差しは、
まさにギナマに送ったそれと同じものだった。
「洋子が死んだ… 」
孝史の言葉に、
一枚の家族写真を見つめていた父は、
いきなり母の名前をつぶやいた。
顔は青ざめ、写真を握った手が震えている。
「柳井さん、記憶が戻ったのかい。」
その様子に、多恵が驚いたような顔をして口を出している。
「いえ… だけど何故かこの人の名前が…
洋子と言う名前が浮かんで来ました。
きっと私が愛した人なのでしょう。
私のせいで不幸になったのですね。
どう償ったら良いのか…
何も覚えていない自分が恨めしいです。」
そう言いながら父は、
頭を抱えて苦しそうな表情を浮かべている。
思い出したくても思い出せないもどかしさ、
悔しさにさいなまれているようだ。