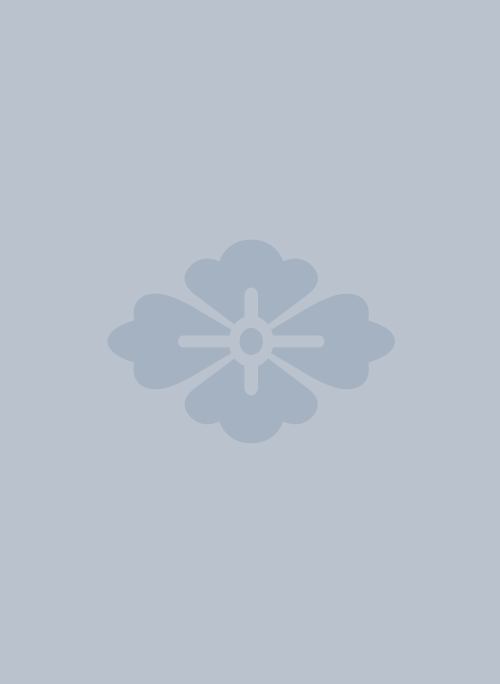ーー元治元年(一八六四年) 十月下旬
京都・壬生村、早朝の新撰組屯所内の炊事場からは食欲をそそる匂いが漂っていた。
「…伊東大蔵?」
「正確に言うと、今は伊東甲子太郎になったらしいんだけどね」
「そないけったいな名前めんどくさくて覚えてられんわ」
「…特徴がありすぎて覚えると思うよ。普通」
この日、朝食の当番に当たっていた楓は、まだ完全に覚醒してない頭で包丁を扱っていた。
「で、そいつが今日ここに来るんか?」
「うん、夕方に。近藤局長と一緒にね」
楓の包丁使いを気にかけつつ、竈で火の調節をしているのは、一番隊隊士の有定武次。
彼は、楓と同期に入隊した商家出身の隊士である。そして平隊士の中では唯一といえる、楓を微塵も恐れない強者であった。
「何でもね、文武両道をそのまま形にしたような人らしいよ」
器用に蒸気の加減を見て、火の具合を操作する有定。
「へー」
明らかに興味なさそうな生返事をする楓は、まな板の上の野菜と格闘していた。
刀は自由自在に操れる楓だが、調理包丁となると話は別であった。
楓は炊事、洗濯、掃除全てにおいて信じられないほど手際が悪いのだ。
今も、人参を乱切りにするだけだというのに相当の時間を要している。