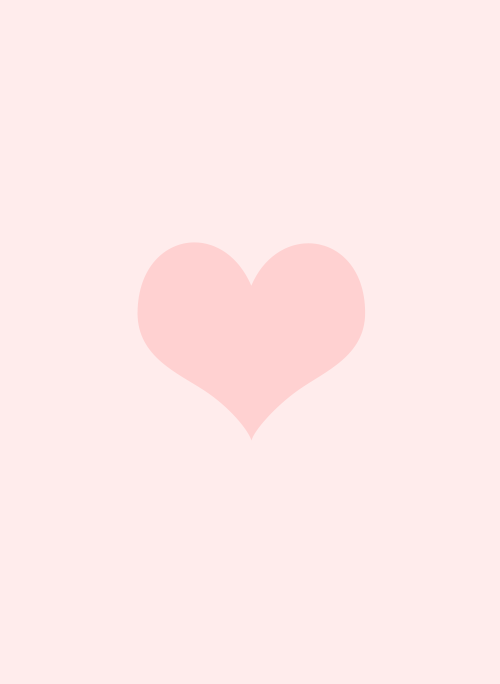いたのは予想通りの人物。
キストが包丁を握りしめ、私を見つめていた。
「みーつけた」
口端を緩めた彼は安心しきっていたようだが、私は震えてしまう。
「キスト……」
「リディア、続きをしよう。場所も丁度いい。昨晩と同じだ、ハハッ。あーでもその前にぃ。
要らない奴を処分しようか!」
「ちっ。キスト、やめるんだ」
「黙れと言っているだろう、下等犬がっ。お前は俺には逆らえないはずだ。今すぐ自害しろ、さあ、さあさあさあ!」
「やめなさい、キスト」
前に出る。
そうしたことでハザマさんに腕を引かれた。
「俺の後ろにいろ、お前に何かあってはウィリアムに顔向けができない」
「ハザマさん……」
「リディアに触れるなっ。彼女は俺のものなんだ!触れていいのは俺だけ、独占してもいいのも俺だけだ!」