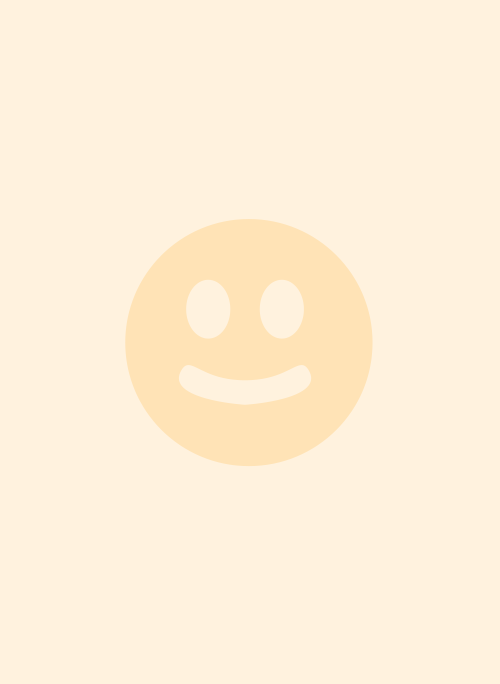わたしは、部屋のカギをかけた。
どうして父があんな目でわたしを見るのかわからなかった。
わたしは、娘なのだから。
舐めるような視線で全身を見られると背筋に悪寒が走った。
「聖也は、お母さんに似てきたな。」
その頃の父の口癖。
わたしは、その言葉を聞くのが無性に嫌いだった。
わたしを棄てた女に似てるなんて。
絶対にイヤだった。
かすかに憶えてる母の記憶。
買い物に行ってくるとわたしに棒付きの飴をくわえさせた。
わたしは、となりのおばさんの家に預けられた。
幼いながらに憶えているお母さんとの最後の時。
それなのに、お母さんの顔は記憶の中でぼやけてはっきりしない。