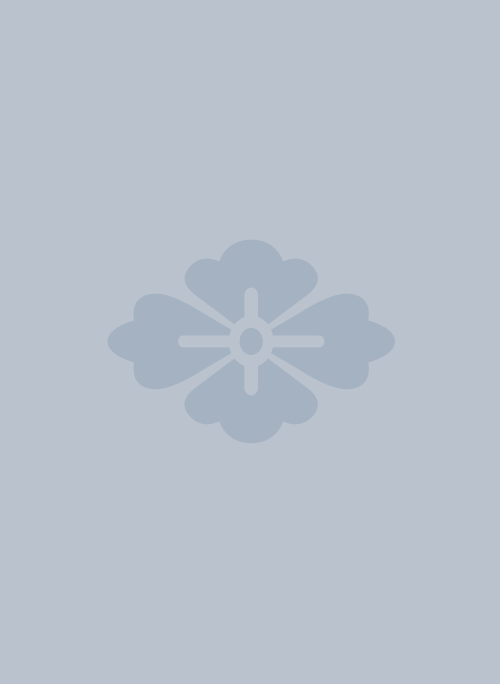――トントン…
「藤堂です」
「……入ってくれ」
(…機嫌悪いなぁ)
意を消して小突いた襖からは、藤堂の勇気を削ぎ落とす暗い声が聞こえた。
「失礼します」
藤堂は緊張で冷たくなった手で襖をそろそろと開く。
「…もっと普通に入って来れねぇのか?」
襖を開けたことで多少光が入った部屋には、煙管を咥えたまま藤堂のゆっくりとした動作に呆れ顔の土方の姿があった。
「いや…だって土方さん機嫌悪そうだし」
「悪い」
「やっぱり…」
胡坐をかいた体勢で忙しなく貧乏揺すりをしている土方の下座におずおずと座る藤堂。
眉間の皺の深さかさ見て、土方は大分ご立腹のようだ。人を殺めた罪人のような鋭い目つきでギロリと藤堂の顔を見る。
(もし俺が童だったら完全にちびってるな…)
正直、成人している今でもこの気迫には耐え難かった。
「藤堂君、君は、死番好きだよな?」
「…その質問明らかにおかしいでしょう?!
まあ、嫌いじゃないですけど」
藤堂はいつもの癖で反射的につっこみを入れてしまった。
土方のいう“死番”とは、捕り物の際に、真っ先に突入する役の人物を指す新撰組内のみで使用される造語であった。
当然、先頭に立って敵地に突っ込む訳だから、後ろについてくる隊士よりも斬られる確立は桁違いに高い。だが、死番を務めた者には、それ相応の報酬が支払われるというメリットもあり、故郷にいる家族に仕送りをする者や、女遊びが激しい者などはその金資目当てに率先して死番に回っていた。
しかし、この藤堂平助は少し違う。
特に女遊びが激しい訳でもなく、実家に仕送りをする訳でもない。それにも関らず、組内で一番死番を務める回数が多いのはこの男なのだ。