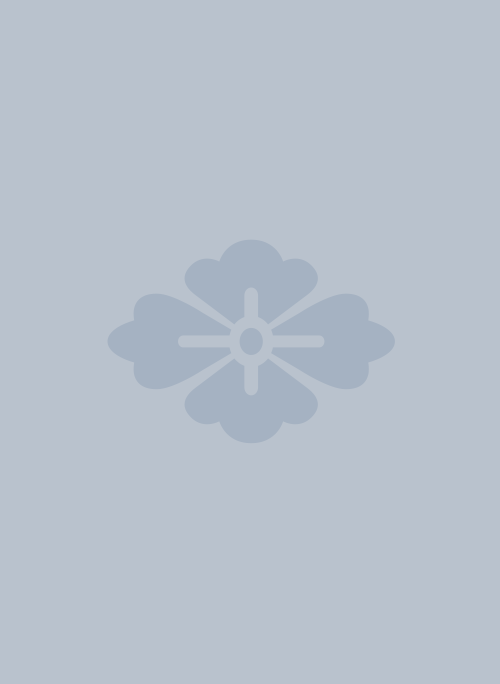「話はそれだけですか?」
ふっと髪を揺らして顔を上げた楓は近藤に尋ねる。
「ああ。もう下がってよいぞ。明日はきっと慌しくなる。ゆっくり休むといい」
「局長も、少し休まれた方がいい。目元、狸みたいになってますよ」
部屋を出ようと起立した楓は、近藤に向けて自分の眼下を人差し指で示した。
「かっかっか!!なーに心配には及ばん!このくらいでどうにかなるほど軟じゃない!!」
近藤は大口を開け、膝をバシバシ叩いて大笑いする。
「どうやら、いらぬ心配をしてしまったようですね」
楓は、馬鹿にするなという意味を込めて笑っているのだと思い、軽く頭を下げて襖に手をかけた。
「赤城君」
襖を自分の体分だけ開け、正に部屋を出ようとした時、近藤から楓に声がかかった。
「君が心配してくれたお陰で、このクマも明日にはすっかり消えているだろう!ありがとう」
「!!」
振り返った楓の顔は行灯の柔らかい光により、薄い橙色に染められた。だが、この色は行灯のせいだけではない。
土方は、暗いためにぼやけた楓の頬の辺りが妙に濃い橙色をしている事に気がついた。
(…なんつー顔してんだこいつは)
土方が見たもの。それは、無表情だが、純真で子どものような顔をした楓であった。
――あれが、赤城楓の本当の顔
確信に近い直感。楓のその表情はほんの一瞬だった。またいつものようなに人を寄せ付けないきりっとした顔に戻る。
(何があいつをここまでにしたのか…?)
今の表情を見た事で、土方の好奇心が駆り立てられた。だが、極端に自分の事を話したがらない楓から何かを聞き出すのは不可能に近い。新撰組の監察の力を持ってしても、何一つ知ることの出来なかった赤城楓という人間。楓の過去に対する気持ちが募る土方だったが、知る術は何もなく、諦めるよりなかった。
「失礼します」
土方が考えを巡らしている間に、近藤との会話を終えた楓は、静かに局長室から出て行った。