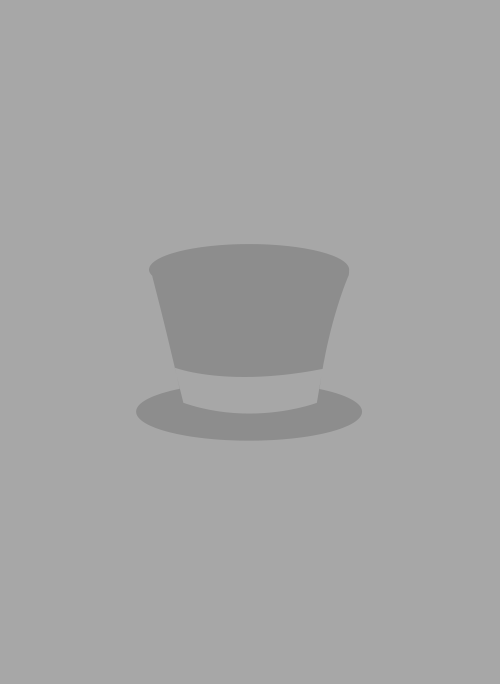「そう言えば… 今思えば確かに、
どこかこそこそとしたところがありましたよ、望月さん。」
そう言って望月と京介を見ながら声を出したのは、
一組の教室で増田と話していた、
黄色のTシャツを着た渡辺三郎だった。
「本当か。渡辺は同じクラスだからなあ。
知っていることがあるのか。」
確かに望月は何も気がついていなかったようだ。
その証拠に渡辺の言葉に一番早くに反応した。
京介は黙ってその場の会話に耳を傾けている。
仲間内の方が話も出易いものだ。
「いえ、知っているとまでは…
でも、一学期の後半ぐらいから
時々教室を抜け出していましたよ。
俺はてっきり望月さんの所へ行ったのか、と思っていました。
だから山田に、何か連絡があったのかと聞いたけど、
何も無かったと言っていた。
どこへ行ったのかと思ったことが度々ありました。
あるとき、いきなり姿がみえなくなったから、
戻って来た増田に聞けば、あの時は、
望月さんに話があった、と言っていました。」
「俺はあいつ一人に声をかけることはしないし、
あいつと二人で会った事も無いぞ。」
望月が京介を意識しているのか、
自分の無関係さを声を上げて主張しているような顔をしている。
「わかっていますよ。
だから、あいつ、おとなしいから、
気に入った女でも出来て見に行っていたのか、
と思って何も言わなかったですけどね。」
渡辺なりに感じていた事を口にしている。
「そう言えば… 俺も見たなあ。
二学期の始まった頃だったか、
あいつが二年生とこそこそ話をしていた。
だけど俺が近付いたらすぐ分かれてしまった。
どうした、と聞いたら、
落し物を二年生が届けてくれた、と言っていたが… 」
と、四組の大下和夫という子分が思い出した。