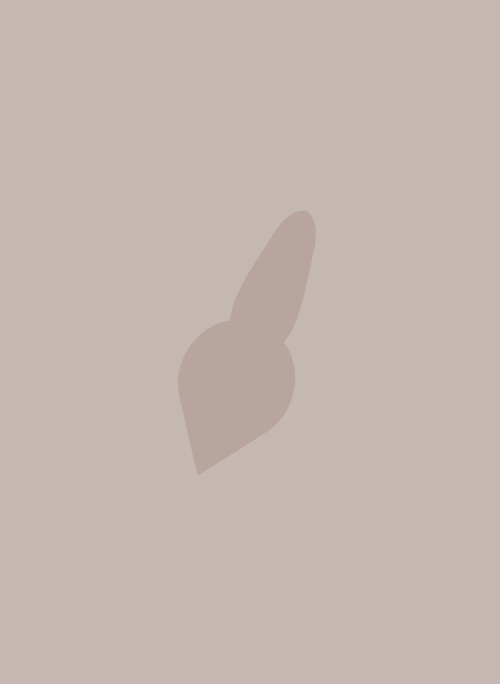佐光は35歳のアラフォー直前ながらも、その童顔とテンションのはっちゃけぶり、そしてたまにのドS君臨で、女子生徒に絶大な人気を誇っている。
親しみやすさからなのかわからないが、勿論男子生徒にも慕われている。
若き日にスクールカウンセラーの資格も取った彼は、生徒の良き相談相手にもなっている。
要するに、先生と言うより友達感覚。
だからため口も当たり前だし、多少の暴力だって遠慮していない。
…そこら辺はうちだけのような気もするが。
ま、ぶっちゃけガキだ。
「…心の声全部漏れてんぞ。」
いつの間にか隣に来ていた智士が、佐光にバレないように小声で耳打ちしてきた。
見上げると、ニヒルな笑顔を浮かべてて。
智士の顔を近くで見上げたら、急に頭が痛くなって。
「…うち、帰る。」
気付けばそう冷たく言い放っていた。
いきなり発したうちの言葉が唐突すぎたのか、声色に疑問を感じたのか、佐光も智士もキョトンってしてる。
その智士の顔ですら、気持ち悪く感じて。
「大丈夫か、」
「かばん、貸して。」
智士の言葉を遮って、再び冷たい声色で催促する。
…そんな困惑を露にした目で見ないでよ。
自分でも何でこんなこと言ってんのか、わかんないんだもん。