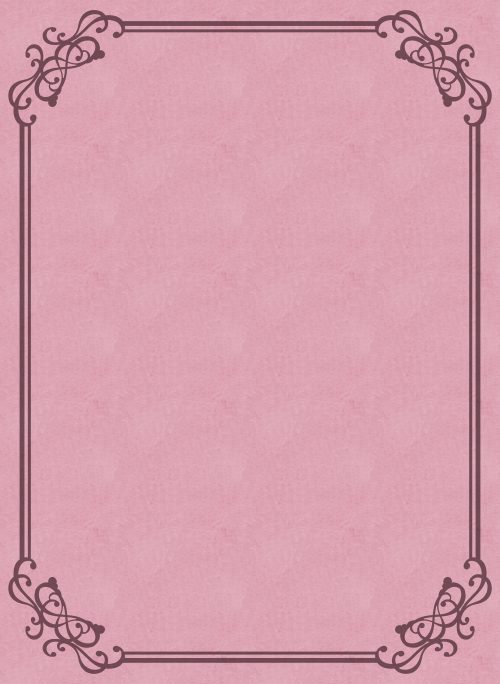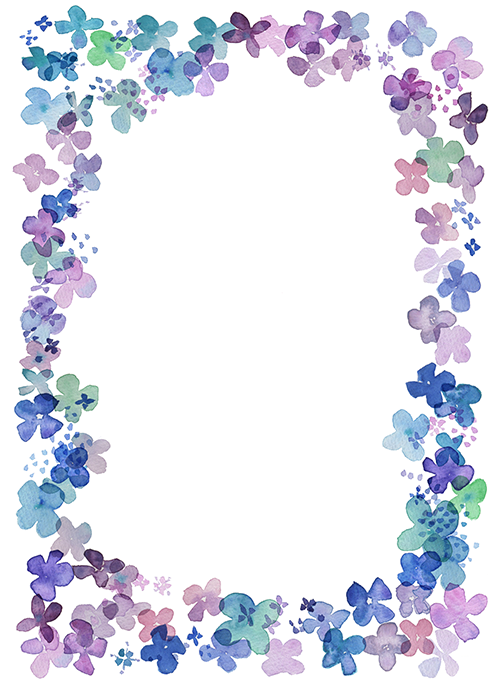灰色の煙を吐き出しながら、俺達を降ろしたバスが去って行った。
静まりかえる住宅街に、ぽつんと二人立ち尽くす。
「家、何処?」
とりあえず訊いてみた。
「……」
「こんな時間だし、家に帰れなくなったら困るじゃん?」
精一杯気をつかいながら、そっと告げると。
「ごめんなさい!
こんなところまで着いてきてしまって……本当にごめんなさい!」
いつかのようにペコペコと頭を下げる彼女の、いまにも泣きだしそうな声と頼りなげな小さな肩に一層躊躇いを感じた。
「それよりさ、今は帰ることを…」
そう言いかけた時。
「ううっ」と嗚咽混じりの声が隣から漏れて、驚く俺を余所にその声は次第に大きくなりやがて大音量に変わった。
「ごめんなさーい!」
本当にまるで幼い子供みたいに、マジ泣きしだした彼女。
どうにもできず俺は、ただ隣でたじろぎ立ち尽くすしかなかった。