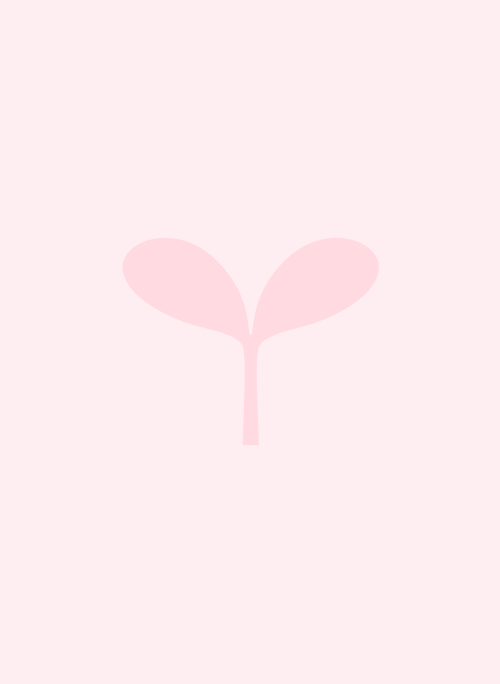「迷惑かけて、・・・ごめんなさい」
その言葉に、胸が締め付けられるほど、心が切なくなる。
何も迷惑ではないというのに。
謝る理由も、何処にもないというのに。
許されるのならば、ずっとこうして 彼女に触れていたい。
「・・・あたしの事は、気になさらないでください」
「何故、そんな事を言うんだい」
熱のせいによってなのか、はたまた 悲しい想いが彼女の心を覆っているせいなのか、
「王子様が・・・・奴隷の事を心配するなんて、駄目です。 身分が、違い過ぎますから」
涙を流し、けれど真っ直ぐと その潤った瞳で、彼を見つめる。
「シンデレラ・・・・」
あぁ、やはり、信じてはもらえない。
こんなにも、君が愛しいというのに。
「いつもみたいに、他の女の人の所へ、どうぞ行ってください」
その言葉に、
「・・・・・いつもみたいに?」
彼はまったく理解が出来ず、首を傾けたまま固まってしまった。