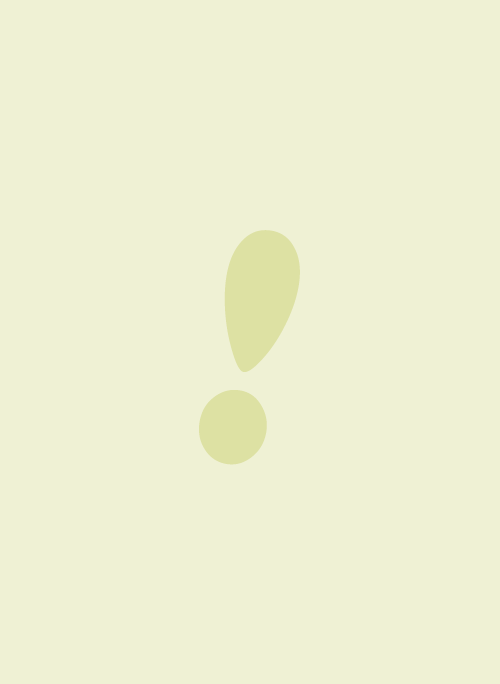「ねぇ、わたしのこと、どれくらい好き?」
「この部屋のあっちからこっちまで、好きだよ」
「わたしなんか、この式場のあっちからこっちまで」
「僕なんか、宇宙のあっちからこっちまで」
だめだ、だめだ!
百合は質問シミュレーションを途中で強制終了させた。
この会話は、まさに頭にバが付くカップルの会話だ。
「ねぇ、わたしが死んじゃったらどうする?」
「僕も死んじゃう~」
だめ、これもだめ!
「どうしたの、ユリ。元気ないよ?」
人生最高の日には似つかわしくない、沈んだ面持ちの百合の顔を、卓也がのぞきこんだ。
「タクは・・・」
何と聞いたらいいかまだ結論が出ないまま、百合は口を開いた。
「・・・いつから、わたしの事を好きだった?」
気づいたら、そう聞いていた。
「え?」
卓也の目が、一瞬泳いだ。
タク、あなたはなんて答えるの?
「君と同じ」?
「分からない」?
「忘れちゃった」?
卓也の答えを聞くのが怖くて、百合はうつむいた。
「・・・」
卓也は少し黙って考えていた。
それから、なぜか笑い出した。
「あのね」