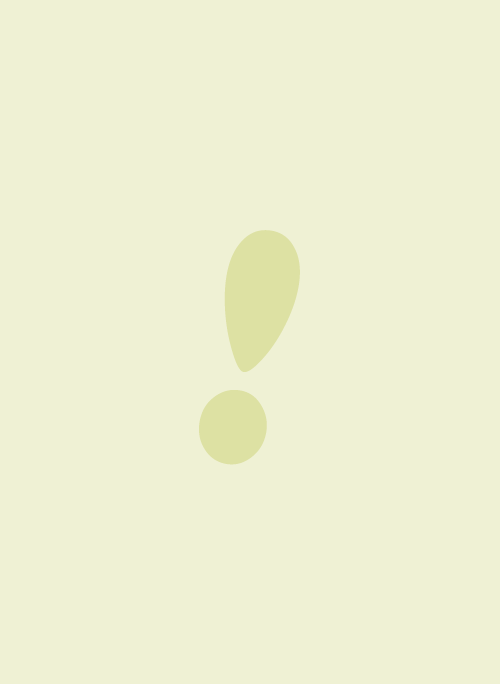「さびしいじゃろうに、外国に一人で。」
ミサエは、すっかり英語(っぽい日本語)を捨て、いつもの話し方でポツポツ喋る。
もちろんジョージには冒頭の「GEORGIA」以外何も分からないのだが、そんなことはもはやお構いなしだ。
あきらめの境地に立った老人は、ある意味最強である。
ジョージのほうも、ミサエの言葉を理解するのはあきらめてBGMのように聞き流す。
「言葉も分からんしなぁ」
「友達も、あまりおらんようだしなぁ」
低い、しわがれた声。
でも、なんだかあたたかい声。
途切れ途切れに発せられるミサエの声は、ジョージの呼吸に合わせるようにジョージの体の中に入っていく。
ミサエは、ジョージの背中にそっと手をかけた。
そして、言った。
ここ何週間か、なんとか伝えようとしてきたことを。
とびきりの優しさを添えて。
「このミサエばあちゃんを、あんたのお母さんだと思ったらえぇ」