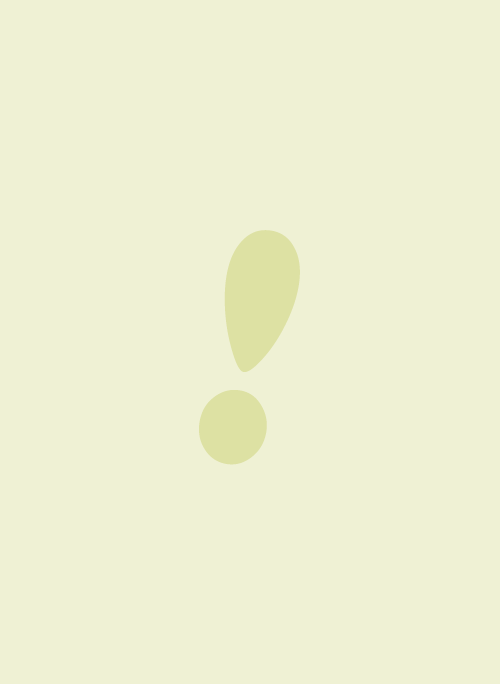「真吾!」
敦子は、持ち上げたばかりのゴミ袋を、また床に落とした。
真吾が、そこに立っていたのだ。
真吾は、もともと人の良さそうな顔の表情を一段と暗くして、一般市民がイメージする「本当に申し訳なさそうな顔」そのものになっていた。
「ごめん、敦子。俺が悪かったよ」
真吾がその謝罪の言葉を言うか言わないかのうちに、敦子は真吾に抱きついていた。
「真吾、ごめん。私も悪かった」
そのまま、わっと泣き出す。
あたし、気づいたんだ、あんたの気持ちに。
あたし、気づいたんだ、あたしの気持ちに。
あんたがあたしのこと、どんだけ大切に思ってくれてたか。
あたしがあんたのこと、どんだけ大切に思ってたか。
センセーのあの一言でさ。
「その元カレの方は、とても大切な方なんですね」
「そんなにたくさんの物をもらったのに、それを全部覚えていらっしゃるなんて。」
そう、あたし、あんたにもらったもん全部、ちゃんと覚えてたから。
いつ、どこで、どんな風にくれたかも、全部。
ありがと、センセ。
真吾は、「その元カレの方」みたいな、ご丁寧な奴じゃないけど。
あたしにとっては、大切な奴なんだ。
宝物を、あたし捨てるとこだったよ。