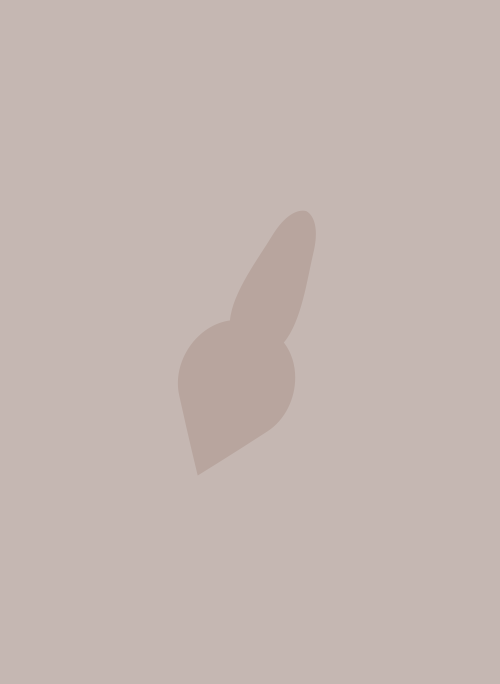「美波はどうしたいの?」「分かんない。私のことが好きじゃなくなったんならどうしようもないじゃん。」
そう言うや否や美波は泣き始めた。彼女の涙を見るのは何年ぶりだろう。柚月は思い出そうとしたが、美波の泣き声が大きくなったので思い出せなくなった。
「あんた、いつからそこらの普通の女になったわけ。」
「仕方ないじゃない。私だってただの女だったってことよ。」
「違うよ。あんたは最高に意地悪で次から次へと悪巧みを生み出す天才でしょ。一体今まで何人の女の子の恋を潰したと思ってるの。そのあんたがありきたりな失恋で終わっていいわけ?」
美波は顔はもう情けなくなかった。何か思いついたときの、最高にいい顔だ。
「柚月のくせに言ってくれるじゃない。」美波がニヤリと笑った。
「だてにあんたの友達やってきたわけじゃないからね。」
それを聞いた瞬間、美波は優しく微笑み、席を立ち上がり、扉へ。取っ手を取り彼女は立ち止まり、振り返らずに呟いた。
「ありがと、親友。」
美波は店を出た。ブーツの音がだんだん遠くなっていく…。
(あんたのそういうとこ好きだよ)柚月は鞄から日記を取り出し、続きを書き始めた。
二人の会話が聞こえたのは柚月が美波を罵ったときだ。あんなこと言っちゃったら明日はないよと思いながらひやひやした。でもよかったね、美波。少し寂しいけど。私も二ヶ月前まであの会話の中にいたのにな。私の罪は重い。あの写真が本物かどうか、暴いて美波に報せれば赦してもらえるだろうか。そんなことを考えながらカップを手に取ったが、中は空だった。
そう言うや否や美波は泣き始めた。彼女の涙を見るのは何年ぶりだろう。柚月は思い出そうとしたが、美波の泣き声が大きくなったので思い出せなくなった。
「あんた、いつからそこらの普通の女になったわけ。」
「仕方ないじゃない。私だってただの女だったってことよ。」
「違うよ。あんたは最高に意地悪で次から次へと悪巧みを生み出す天才でしょ。一体今まで何人の女の子の恋を潰したと思ってるの。そのあんたがありきたりな失恋で終わっていいわけ?」
美波は顔はもう情けなくなかった。何か思いついたときの、最高にいい顔だ。
「柚月のくせに言ってくれるじゃない。」美波がニヤリと笑った。
「だてにあんたの友達やってきたわけじゃないからね。」
それを聞いた瞬間、美波は優しく微笑み、席を立ち上がり、扉へ。取っ手を取り彼女は立ち止まり、振り返らずに呟いた。
「ありがと、親友。」
美波は店を出た。ブーツの音がだんだん遠くなっていく…。
(あんたのそういうとこ好きだよ)柚月は鞄から日記を取り出し、続きを書き始めた。
二人の会話が聞こえたのは柚月が美波を罵ったときだ。あんなこと言っちゃったら明日はないよと思いながらひやひやした。でもよかったね、美波。少し寂しいけど。私も二ヶ月前まであの会話の中にいたのにな。私の罪は重い。あの写真が本物かどうか、暴いて美波に報せれば赦してもらえるだろうか。そんなことを考えながらカップを手に取ったが、中は空だった。