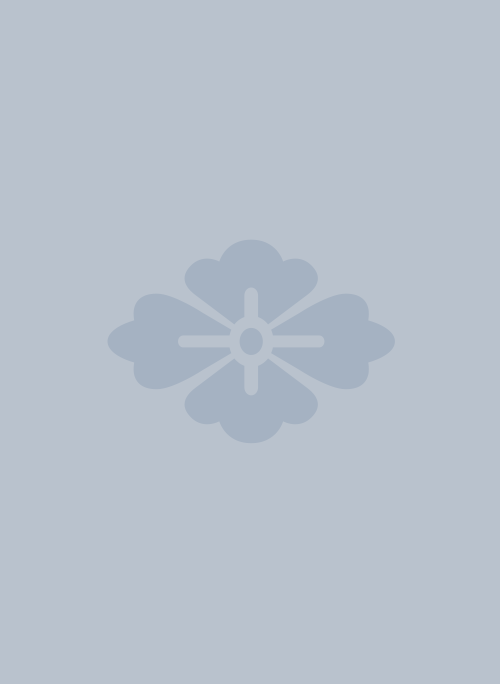「おぅよ。もっとも、あっちの客かもしれんがな」
「そんなん、仕事場には来ないだろ? 単純に、腕が良いからじゃないのか?」
与一の言葉に、三郎太は、ずいっと顔を近づけた。
「腕が良いのも確かだけどな。あそこの店は、結構乱れてるぜ。仕事中でも、二人で奥に消えたら、怪しいと思う」
「店の奥? でも、奥は住まいだろ? 奥方もいるんじゃないのか?」
与一も、身を乗り出した。
さっきまでは、まるで話にならなかったが、思わぬところから核心に迫ったものだ。
三郎太は、ぐんと声を潜めた。
「あそこの奥方は、昼間はずっと出かけてるんだよ。うちのお嬢さんと友達でな、いつもうちの駕籠を使ってくださるから、どこに行ったか、まるわかりなんだ」
「そんなん、仕事場には来ないだろ? 単純に、腕が良いからじゃないのか?」
与一の言葉に、三郎太は、ずいっと顔を近づけた。
「腕が良いのも確かだけどな。あそこの店は、結構乱れてるぜ。仕事中でも、二人で奥に消えたら、怪しいと思う」
「店の奥? でも、奥は住まいだろ? 奥方もいるんじゃないのか?」
与一も、身を乗り出した。
さっきまでは、まるで話にならなかったが、思わぬところから核心に迫ったものだ。
三郎太は、ぐんと声を潜めた。
「あそこの奥方は、昼間はずっと出かけてるんだよ。うちのお嬢さんと友達でな、いつもうちの駕籠を使ってくださるから、どこに行ったか、まるわかりなんだ」