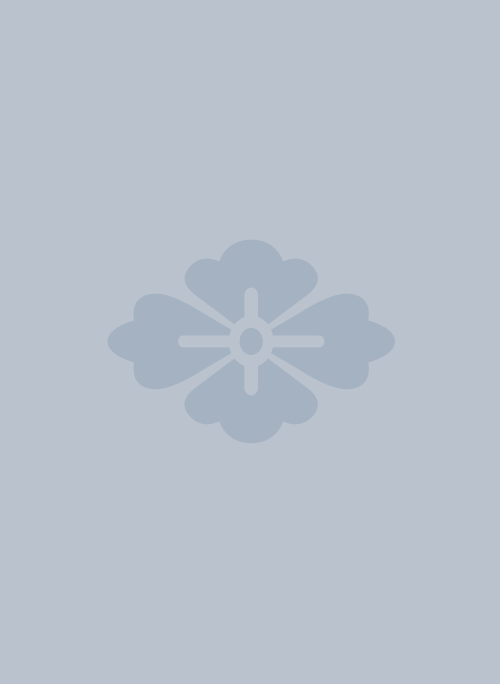「へえぇ。そんなにかい」
見た感じは、うだつの上がらない、冴えない職人という感じだが、そこまで旦那に好かれているのなら、大事なものを預けることもあるかもな、と、与一はちらりと背後を振り返った。
「おいおい。今の言葉に、何も食い付かないのか、お前は」
ふと見ると、三郎太が不満げに覗き込んでいる。
はて、何かおかしなことがあったろうかと考える与一の耳元で、三郎太は小さく言った。
「公私ともってことは、あそこの旦那と辰巳は、尋常ならざる関係だってことだよ」
「? あそこの旦那ってのは、女なのか? 女主人の店だったのか?」
途端に三郎太が、ばん、と与一の背中を叩いた。
「違ぇーよ。男さね。男同士で、怪しいってこった」
与一は目を剥いた。
男色というのは、坊主の世界だけではなかったのか。
見た感じは、うだつの上がらない、冴えない職人という感じだが、そこまで旦那に好かれているのなら、大事なものを預けることもあるかもな、と、与一はちらりと背後を振り返った。
「おいおい。今の言葉に、何も食い付かないのか、お前は」
ふと見ると、三郎太が不満げに覗き込んでいる。
はて、何かおかしなことがあったろうかと考える与一の耳元で、三郎太は小さく言った。
「公私ともってことは、あそこの旦那と辰巳は、尋常ならざる関係だってことだよ」
「? あそこの旦那ってのは、女なのか? 女主人の店だったのか?」
途端に三郎太が、ばん、と与一の背中を叩いた。
「違ぇーよ。男さね。男同士で、怪しいってこった」
与一は目を剥いた。
男色というのは、坊主の世界だけではなかったのか。