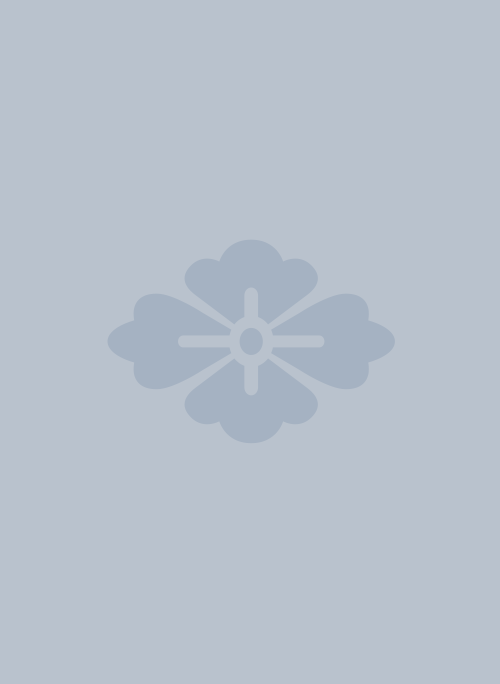「お三津は、お前の姉みたいなもんだったからなぁ」
与一もお三津を不憫に思い、やりきれなさに項垂れたのだと思った三郎太が、与一の肩を叩いてしみじみ言った。
与一は下を向いたまま小さく笑い、身体を起こした。
「女郎だったら、いつでも会いに行けるぜ。三郎太、身請けしてやりゃいいじゃねぇか」
「ば、馬鹿を言うな」
赤くなって慌てる三郎太は、しきりに頭を掻きながら、しばらく視線を彷徨わせた後、照れくさそうに口を開いた。
「実はな、千秋屋のお嬢さんが、俺のことを気に入ってくれてな」
言いながら、膝に置いた風呂敷包みを、そっと開いた。
赤味がかった橙色の、少し小さめの下駄。
与一もお三津を不憫に思い、やりきれなさに項垂れたのだと思った三郎太が、与一の肩を叩いてしみじみ言った。
与一は下を向いたまま小さく笑い、身体を起こした。
「女郎だったら、いつでも会いに行けるぜ。三郎太、身請けしてやりゃいいじゃねぇか」
「ば、馬鹿を言うな」
赤くなって慌てる三郎太は、しきりに頭を掻きながら、しばらく視線を彷徨わせた後、照れくさそうに口を開いた。
「実はな、千秋屋のお嬢さんが、俺のことを気に入ってくれてな」
言いながら、膝に置いた風呂敷包みを、そっと開いた。
赤味がかった橙色の、少し小さめの下駄。