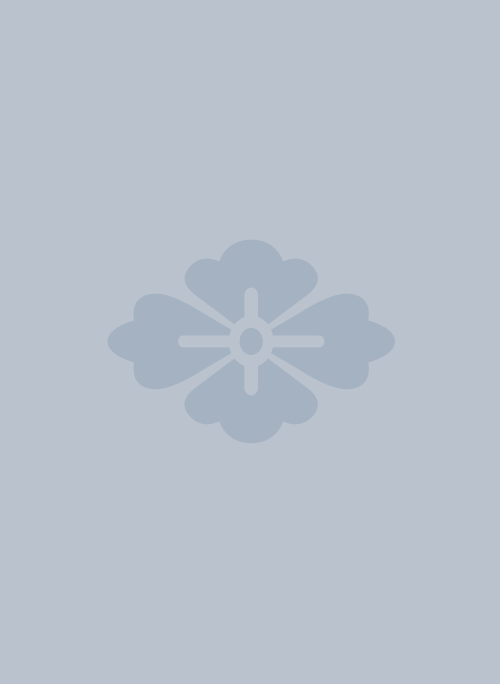二人が通されたのは、二階の座敷の奥、通常の座敷とは襖を隔てた、十畳ほどの個室だった。
窓からは、思った通りばっちりと、件(くだん)の店が見える。
「で? よいっちゃんの感想は?」
窓辺にもたれ、注文した稲荷寿司にかぶりつきながら、藍が問う。
普段はあまりものを食べない藍だが、何故だか稲荷寿司だけは、よく食べる。
「から公の手紙には、何て書いてありましたっけ」
山菜のおこわと魚の干物に箸をつけつつ、与一は質問を質問で返した。
えっとね、と、慌てて持っていた稲荷寿司を口に放り込み、ぺろりと指先を舐めながら、記憶を探る。
その仕草一つ一つが、見かけの年相応に子供じみていて、可愛らしくはあるが、頼りなくもある。
とてもこの美少女が、与一の師匠であり、与一よりも腕の立つ殺し屋などとは、言われたところで、とても信じられないだろう。
与一はそっと、視線を窓の外に戻した。
「小物街三番の下駄屋にある‘御珠’を取り戻したく。御珠は、我が主(あるじ)の願いを聞きし宝なり。下駄屋の亭主、職人の辰巳(たつみ)に御珠預けしこと、確認す。辰巳、腕利きなり。御珠狙いし輩(やから)、ことごとく打ちのめさる。かくなる上は、辰巳亡き者にし、御珠取り返す所存。が、まずは御珠第一。辰巳の始末は、状況次第」
頭に入っている文を読み上げ、新たな稲荷寿司をつまむと、藍もまた、窓の外に視線をやった。
窓からは、思った通りばっちりと、件(くだん)の店が見える。
「で? よいっちゃんの感想は?」
窓辺にもたれ、注文した稲荷寿司にかぶりつきながら、藍が問う。
普段はあまりものを食べない藍だが、何故だか稲荷寿司だけは、よく食べる。
「から公の手紙には、何て書いてありましたっけ」
山菜のおこわと魚の干物に箸をつけつつ、与一は質問を質問で返した。
えっとね、と、慌てて持っていた稲荷寿司を口に放り込み、ぺろりと指先を舐めながら、記憶を探る。
その仕草一つ一つが、見かけの年相応に子供じみていて、可愛らしくはあるが、頼りなくもある。
とてもこの美少女が、与一の師匠であり、与一よりも腕の立つ殺し屋などとは、言われたところで、とても信じられないだろう。
与一はそっと、視線を窓の外に戻した。
「小物街三番の下駄屋にある‘御珠’を取り戻したく。御珠は、我が主(あるじ)の願いを聞きし宝なり。下駄屋の亭主、職人の辰巳(たつみ)に御珠預けしこと、確認す。辰巳、腕利きなり。御珠狙いし輩(やから)、ことごとく打ちのめさる。かくなる上は、辰巳亡き者にし、御珠取り返す所存。が、まずは御珠第一。辰巳の始末は、状況次第」
頭に入っている文を読み上げ、新たな稲荷寿司をつまむと、藍もまた、窓の外に視線をやった。