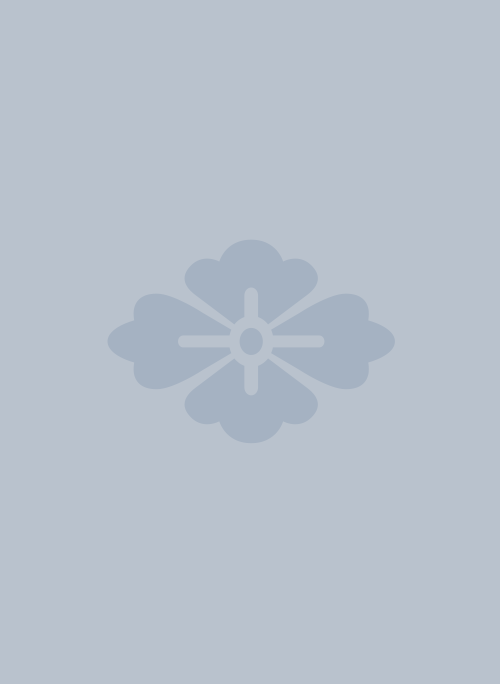「何なのよぅ。あたしが引っ付いたら、嫌なの?」
藍が顔を上げて、与一を睨む。
が、初めて見る与一の泣きそうな顔に、藍は目を見開いた。
「ど、どうしたのよ。傷が痛むの? 気分でも悪い?」
がばっと上体を起こそうとする藍を、与一はまた慌てて引き留めた。
だが慌てたため、ぐい、と抱きしめるかたちになる。
それしか方法がなかったといえばそうだが、与一は己の胸に感じる柔らかさに、再び悲鳴を上げそうになった。
「よいっちゃん? ちょっと、大丈夫なの? どうしたの?」
「わーっ、ら、藍さん。動かないでっ・・・・・・て、そもそも何でそんな格好で・・・・・・いや、俺がやったんなら謝りますけどっ」
いつにない与一の行動に、藍が心配してごそごそ動くのを必死で止めながら、与一は早口でまくし立てた。
己の熱と、藍の感触に、気が遠くなりそうだ。
「ついさっきまで、意識のなかったよいっちゃんが、何したっていうのよ。よいっちゃんに謝ってもらうことなんて、何もないわよ? あ、もしかして、仕事の途中で気絶しちゃったの、気にしてるの?」
無邪気ともいえる顔を向ける藍に、与一は気を落ち着かせるべく、目だけを動かして、部屋の中を見回した。
いつも寝ている二階ではなく、どうやら一階の物置部屋のようだ。
ふと目の端に、藍の白い小袖が映った。
与一は片手で藍を押さえつけたまま、そろそろと伸ばしたもう片方の手で小袖を掴むと、それを布団の中に引っ張り込んだ。
藍が顔を上げて、与一を睨む。
が、初めて見る与一の泣きそうな顔に、藍は目を見開いた。
「ど、どうしたのよ。傷が痛むの? 気分でも悪い?」
がばっと上体を起こそうとする藍を、与一はまた慌てて引き留めた。
だが慌てたため、ぐい、と抱きしめるかたちになる。
それしか方法がなかったといえばそうだが、与一は己の胸に感じる柔らかさに、再び悲鳴を上げそうになった。
「よいっちゃん? ちょっと、大丈夫なの? どうしたの?」
「わーっ、ら、藍さん。動かないでっ・・・・・・て、そもそも何でそんな格好で・・・・・・いや、俺がやったんなら謝りますけどっ」
いつにない与一の行動に、藍が心配してごそごそ動くのを必死で止めながら、与一は早口でまくし立てた。
己の熱と、藍の感触に、気が遠くなりそうだ。
「ついさっきまで、意識のなかったよいっちゃんが、何したっていうのよ。よいっちゃんに謝ってもらうことなんて、何もないわよ? あ、もしかして、仕事の途中で気絶しちゃったの、気にしてるの?」
無邪気ともいえる顔を向ける藍に、与一は気を落ち着かせるべく、目だけを動かして、部屋の中を見回した。
いつも寝ている二階ではなく、どうやら一階の物置部屋のようだ。
ふと目の端に、藍の白い小袖が映った。
与一は片手で藍を押さえつけたまま、そろそろと伸ばしたもう片方の手で小袖を掴むと、それを布団の中に引っ張り込んだ。