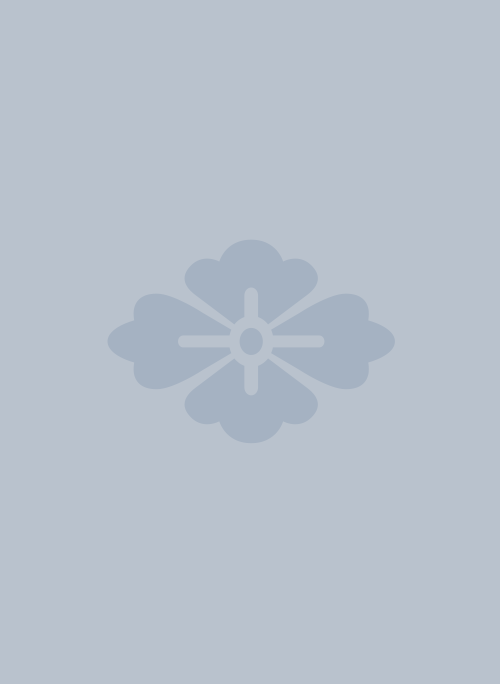「そいで、その比和の守り役のところへ、何で迎えと称して殺し屋なんぞを送り込むんだ。辰巳が邪魔になったのか? そもそも、あんたが次の北御所なら、お福はあんたに仕える斎王じゃないのか。何で家臣が主の守り役を襲うんだ」
黙って聞いていた風弥が、口を挟んだ。
たまは一度、ふぅ、と息をつくと、辰巳の膝の上で丸まり、膝に頭を乗せた。
「・・・・・・順を追って話すかの。わらわは先に述べた通り、次期北の主神。今は妖狐である北御所様が主神じゃ。お福の家は、代々北御所に仕える斎王の家系。といっても、特殊な力があるわけではない、ただの人間じゃ。実際に斎王の地位に就くまでは、主神に相見(あいまみ)えることも許されぬ。故に斎王になるべきお福の家の者も、北御所様が妖狐などと、誰も知らぬ。その辺の神主と同じと思っておるじゃろう。実際斎王の座について、本物の北御所様にお目通りするまではな」
「斎王とはいえ、ただの人間なのだろ? 見えるのか?」
風弥の突っ込みに、たまは鼻を鳴らす。
「お目通りのときだけは、北御所様自ら姿を現す。でないと、お主の言うとおり、只人(ただびと)には見えぬからの」
その後も、たまの話は続く。
藍は与一の傷の手当てをしながら、たまの話に耳を傾けた。
黙って聞いていた風弥が、口を挟んだ。
たまは一度、ふぅ、と息をつくと、辰巳の膝の上で丸まり、膝に頭を乗せた。
「・・・・・・順を追って話すかの。わらわは先に述べた通り、次期北の主神。今は妖狐である北御所様が主神じゃ。お福の家は、代々北御所に仕える斎王の家系。といっても、特殊な力があるわけではない、ただの人間じゃ。実際に斎王の地位に就くまでは、主神に相見(あいまみ)えることも許されぬ。故に斎王になるべきお福の家の者も、北御所様が妖狐などと、誰も知らぬ。その辺の神主と同じと思っておるじゃろう。実際斎王の座について、本物の北御所様にお目通りするまではな」
「斎王とはいえ、ただの人間なのだろ? 見えるのか?」
風弥の突っ込みに、たまは鼻を鳴らす。
「お目通りのときだけは、北御所様自ら姿を現す。でないと、お主の言うとおり、只人(ただびと)には見えぬからの」
その後も、たまの話は続く。
藍は与一の傷の手当てをしながら、たまの話に耳を傾けた。