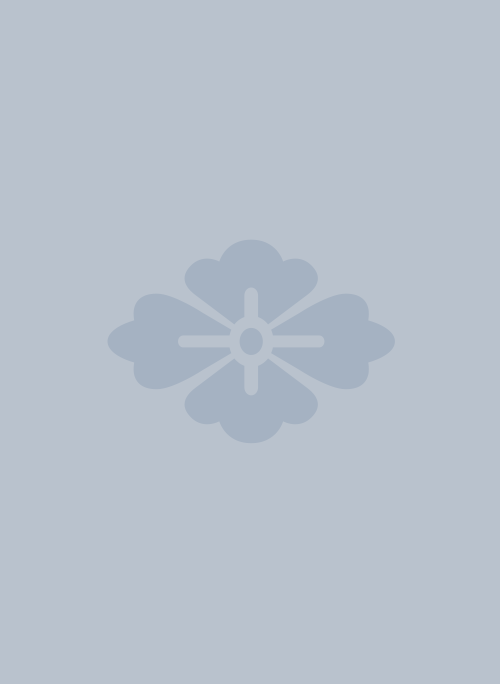「預かってるだけだよ。そんなことより、とにかく手当をしないと」
短く言い、辰巳は懐から出した懐紙で、与一の顔の血を拭った。
「たまって言ったな。その猫を預けたのは、北御所様じゃないのか?」
大人しく辰巳に顔を拭かれながら、与一が言った言葉に、藍も風弥も、口をあんぐり開けて固まる。
辰巳に寄り添う黒猫だけが、肯定するように、にゃあ、と鳴いた。
「ま、まさか、その猫が、御珠・・・・・・?」
「確かに両手で掴めるぐらいの大きさのわりには、重そうだけど」
黒猫をしげしげと眺めて‘重そう’と言った藍を、黒猫がじろりと睨んだ。
そのまましばらく、辰巳以外の三人は、茫然と黒猫を眺めていた。
藍も与一も、御珠というのは、その字の如く、珠のようなものだと思っていたし、風弥も猫と知って驚いていたから、似たようなものを想像していたのだろう。
「猫が願いを叶えるってこと? どういうことなの??」
混乱したように呟く藍の横で、考え込んでいた風弥が、ふぅ、と息をついた。
「何となく、見えてきたぞ」
そう言って、ずかずかと辰巳に近づくと、風弥はいきなり黒猫の尻尾を、ぎゅっと掴んだ。
その途端---。
「にゃにするんだいっ!」
甲高い声が響き、黒猫が二本足で立ち上がった。
短く言い、辰巳は懐から出した懐紙で、与一の顔の血を拭った。
「たまって言ったな。その猫を預けたのは、北御所様じゃないのか?」
大人しく辰巳に顔を拭かれながら、与一が言った言葉に、藍も風弥も、口をあんぐり開けて固まる。
辰巳に寄り添う黒猫だけが、肯定するように、にゃあ、と鳴いた。
「ま、まさか、その猫が、御珠・・・・・・?」
「確かに両手で掴めるぐらいの大きさのわりには、重そうだけど」
黒猫をしげしげと眺めて‘重そう’と言った藍を、黒猫がじろりと睨んだ。
そのまましばらく、辰巳以外の三人は、茫然と黒猫を眺めていた。
藍も与一も、御珠というのは、その字の如く、珠のようなものだと思っていたし、風弥も猫と知って驚いていたから、似たようなものを想像していたのだろう。
「猫が願いを叶えるってこと? どういうことなの??」
混乱したように呟く藍の横で、考え込んでいた風弥が、ふぅ、と息をついた。
「何となく、見えてきたぞ」
そう言って、ずかずかと辰巳に近づくと、風弥はいきなり黒猫の尻尾を、ぎゅっと掴んだ。
その途端---。
「にゃにするんだいっ!」
甲高い声が響き、黒猫が二本足で立ち上がった。