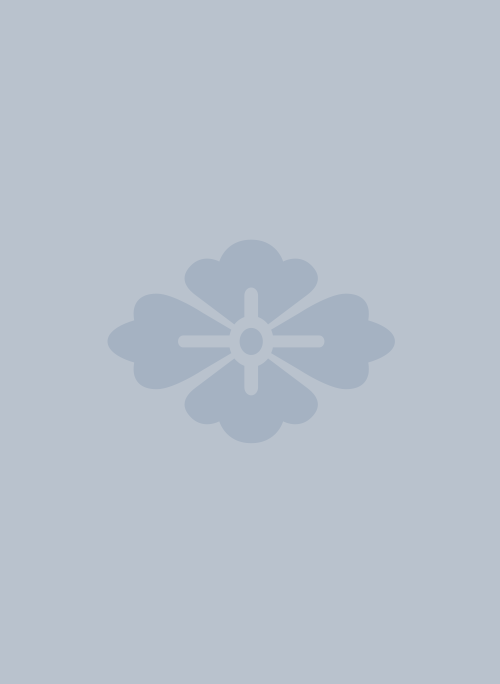襖に手をかけていた朔太郎が、驚いたように藍を見た。
そして、ぱっと笑顔になって、ぶんぶんと首を振る。
「とっとんでもない! こちらこそ、気が利きませんで。どうぞ、お気になさらず!」
ではっ! と勢い良く頭を下げ、襖を閉めると、一転して足音軽やかに去っていった。
「・・・・・・やれやれ。単純な奴だな。彩ちゃん、大丈夫か?」
呆れたように言う三郎太に、藍はこくんと頷いた。
まるっきり子供のように、手の甲でごしごしと涙を拭く藍に、お蓉が微笑み、手ぬぐいを差し出した。
「彩さんは、本当に与一さんがお好きなのねぇ」
「だって、あたしには、よいっちゃんだけだもの」
藍の言葉に、お蓉が目を見開く。
先程の藍の身の上話を思い出し、お蓉は目頭を押さえた。
「あなたはお小さいのに、苦労してこられたのねぇ」
よよ、と泣くお蓉に、藍はきょとんとし、ひらひらと手を振った。
「三郎太さんにも言ったけど、お蓉さんも、あたしの話、信じすぎよぅ。まぁ、あたしによいっちゃんしかいないのは、本当のことだけどね」
先程の藍の身の上話は、まるっきりの嘘ではない。
両親がいないのは本当だし、ただ一人の知り合いが与一というのも本当だ。
「良家のお嬢様には、わかんないかもしれないけど、苦労なんか、してないわよ。あたしは、よいっちゃんさえいてくれれば、幸せだし」
さらりと言った藍に、三郎太もお蓉も、羨ましそうに目を細める。
「与一は本当に、幸せ者だなぁ。そんなこと言ってくれる人間は、そうはいないぜ」
「そうだといいんだけどね」
少し悲しそうに笑う藍に、袂に入れていた包みを手渡し、三郎太はぽん、と藍の頭に手を置いた。
そして、ぱっと笑顔になって、ぶんぶんと首を振る。
「とっとんでもない! こちらこそ、気が利きませんで。どうぞ、お気になさらず!」
ではっ! と勢い良く頭を下げ、襖を閉めると、一転して足音軽やかに去っていった。
「・・・・・・やれやれ。単純な奴だな。彩ちゃん、大丈夫か?」
呆れたように言う三郎太に、藍はこくんと頷いた。
まるっきり子供のように、手の甲でごしごしと涙を拭く藍に、お蓉が微笑み、手ぬぐいを差し出した。
「彩さんは、本当に与一さんがお好きなのねぇ」
「だって、あたしには、よいっちゃんだけだもの」
藍の言葉に、お蓉が目を見開く。
先程の藍の身の上話を思い出し、お蓉は目頭を押さえた。
「あなたはお小さいのに、苦労してこられたのねぇ」
よよ、と泣くお蓉に、藍はきょとんとし、ひらひらと手を振った。
「三郎太さんにも言ったけど、お蓉さんも、あたしの話、信じすぎよぅ。まぁ、あたしによいっちゃんしかいないのは、本当のことだけどね」
先程の藍の身の上話は、まるっきりの嘘ではない。
両親がいないのは本当だし、ただ一人の知り合いが与一というのも本当だ。
「良家のお嬢様には、わかんないかもしれないけど、苦労なんか、してないわよ。あたしは、よいっちゃんさえいてくれれば、幸せだし」
さらりと言った藍に、三郎太もお蓉も、羨ましそうに目を細める。
「与一は本当に、幸せ者だなぁ。そんなこと言ってくれる人間は、そうはいないぜ」
「そうだといいんだけどね」
少し悲しそうに笑う藍に、袂に入れていた包みを手渡し、三郎太はぽん、と藍の頭に手を置いた。