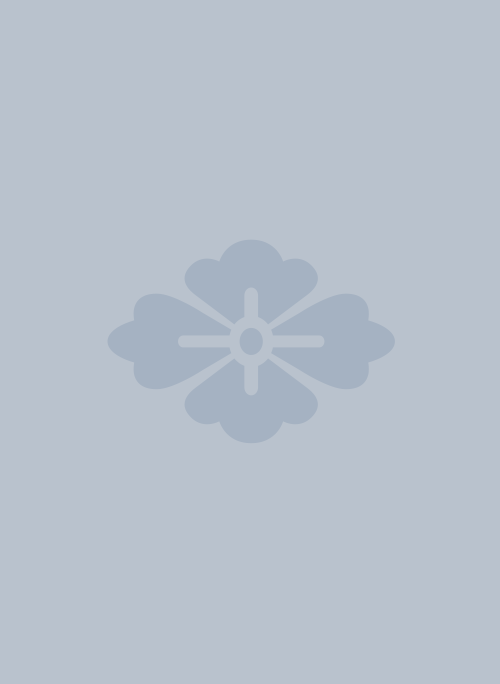「ねぇ三郎太さん。あなたまで、あたしの話を真に受けて、どうするのよ」
廊下を歩きながら、藍が三郎太に言った。
三郎太は、え? と振り向き、すぐに照れたように頭を掻いた。
「あはは、そうか。彩ちゃんは、与一と暮らしてるんだったな。すっかり忘れてたよ。でも、ご両親がいないのは、本当だろう?」
「まぁね。でもそんなこと、あなただって一緒でしょ。よいっちゃんもそうだし、あたしたちみたいな庶民には、珍しいことじゃないわ」
あっさりと言う藍に、三郎太も頷く。
「そうだな。忘れてたよ。それだけいい旦那様に、巡り会えたってことだな」
「そうね。そのいい旦那様たちが、もうじき本当のご両親になるのよね」
赤くなって笑う三郎太が、ふと藍を見て言った。
「そういえば、気分は? 大丈夫なのかい?」
部屋を出た途端、元気になった藍に、三郎太は彼女が気分が悪いと言っていたことを忘れていた。
藍はぴょこんと三郎太を見上げ、にこりと笑う。
「あ、あれも演技。ていうか、あたし、あんなにご飯、食べられないの。美味しかったのは、本当よ」
少し申し訳なさそうに言う藍に、三郎太は目を丸くした。
廊下を歩きながら、藍が三郎太に言った。
三郎太は、え? と振り向き、すぐに照れたように頭を掻いた。
「あはは、そうか。彩ちゃんは、与一と暮らしてるんだったな。すっかり忘れてたよ。でも、ご両親がいないのは、本当だろう?」
「まぁね。でもそんなこと、あなただって一緒でしょ。よいっちゃんもそうだし、あたしたちみたいな庶民には、珍しいことじゃないわ」
あっさりと言う藍に、三郎太も頷く。
「そうだな。忘れてたよ。それだけいい旦那様に、巡り会えたってことだな」
「そうね。そのいい旦那様たちが、もうじき本当のご両親になるのよね」
赤くなって笑う三郎太が、ふと藍を見て言った。
「そういえば、気分は? 大丈夫なのかい?」
部屋を出た途端、元気になった藍に、三郎太は彼女が気分が悪いと言っていたことを忘れていた。
藍はぴょこんと三郎太を見上げ、にこりと笑う。
「あ、あれも演技。ていうか、あたし、あんなにご飯、食べられないの。美味しかったのは、本当よ」
少し申し訳なさそうに言う藍に、三郎太は目を丸くした。